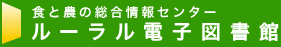No.188 アメリカの有機と慣行のリンゴ生産
●加工用リンゴ生産は減少したが,特に有機の生食用リンゴは増加
アメリカでは1990年代以降,加工用リンゴの中国などからの輸入(主にジュース用)が増加したため,アメリカのリンゴ全体の生産量は1994年をピークに減少している(図1)。そして,リンゴ生産はワシン トン州,ニューヨーク州,ミシガン州とその他のいくつかの州に集中し続けている。 そうしたなかにあって,生食用リンゴの需要は,新しいリンゴ品種(ガラ,ふじ,レッドデリシャス)を中心に増加しており,有機リンゴに対する需要はさらに急速に高まっている。ちなみに,有機食品の販売額は,最近の経済下降期にあっても食品販売額全体を上回る成長を続け,2桁の成長を続けている。有機リンゴは,有機食品消費者の購入する果実の上位3つに入っている。
●植物生育調節剤(ダミノザイド)事件
植物生育調節剤のダミノザイド(アメリカでの商品名はエイラー,”Ala”)は,かつて果実の成熟を促進し,着色を向上させるために,果樹に散布されていた。しかし,1970年代中頃から,この薬剤は分解すると,発ガン性の非対称性ジメチルヒドラジンを生ずることが問題になった。1980年にアメリカの環境保護庁(EPA)はこの問題の検討委員会を開催し,1985年に農薬製剤と非対称性ジメチルヒドラジンの双方が発ガン作物用を持つ可能性が高いとの結論を出した。しかし,販売禁止にしなかったため,引き続いて使用された。そして,ダミノザイドや非対称性ジメチルヒドラジンがリンゴのソースやジュースからたびたび検出された。1989年2月にマスメディアがこのことを報じ,問題を知った消費者ユニオンがその使用禁止を強く求めて,大きな社会問題になった。
メディアが報道した後にリンゴ価格は急速に低下し,当該シーズンのリンゴの収益は1億4000万ドル減少したと推定されている。EPAは,1989年5月に全ての食料品に対してダミノザイドを使用することを取り消す提案を行ない,メーカは翌月から食料品に対するダミノザイドの販売と配送を自主的に中止した。これを受けて,アメリカのリンゴ価格と収益は翌年から急速に回復した。この事件はアメリカの農薬取締に関する法的規制が不十分であるとして,アメリカが農薬規制を強化するきっかけの一つとなった。また,この事件は有機リンゴへの消費者の関心を高めることにつながった。
●農務省の農業資源管理調査
農務省の全米農業統計局 (National Agricultural Statistics Service: NASS)が農業関係の統計を調査しているが,毎年詳しい調査を実施することができない。そこで,全米農業統計局と経済研究局(Economic Research Service: ERS)は,共同で,毎年対象を変え,圃場レベルでの農業生産の方法,農場運営の経理,農場の家族構成などについてより詳しいデータを収集する農業資源管理調査(Agricultural Resource Management Survey: ARMS)を実施している。この調査と毎年の統計調査を重ねることによって,アメリカの農業実態の様々な側面を詳しく解析できる。
2007年にリンゴが農業資源管理調査の対象となり,慣行のリンゴ生産に加えて,毎年の調査では対象外の有機のリンゴ生産も対象にして,農場の概要,家族の特徴,リンゴの具体的な栽培方法,出荷方法などを,現地での聞き取り,アンケート,記録提供依頼などによって調査した。
この調査結果を分析し,「アメリカの慣行および有機のリンゴ生産の特徴」として,経済研究局が2011年7月に刊行した。その概要を下記に紹介する。
2007年の調査では,7つの州(カリフォルニア,ミシガン,ニューヨーク,ノースカロライナ,オレゴン,ペンシルバニア,ワシントンの各州)から回答があった1,060人の有機および慣行のリンゴ生産者について調査を行なった。これらの州の生産者は2007年におけるアメリカのリンゴ収穫面積の81%,リンゴ生産量の87%を占めた。
●州別の慣行と有機のリンゴ生産
調査した7つの州がアメリカにおいてリンゴを生産している主要な州である。西海岸のカナダ国境に接するワシントン州が,現在全米の国内生産リンゴの半分超を生産し,1920年代初期からリンゴ生産のリーディング州となっている。図2は,2007年の農業資源管理調査で調べた7つの州でのリンゴ生産量を図化したもので,7州の慣行と有機を合わせたリンゴ総生産量(408.1万トン)の59.7%がワシントン州で生産されていた。そして,7州の慣行リンゴ(生食用と加工用の和)ではワシントン州が58.5%を占めていた。ワシントン州の慣行リンゴの大部分は生食用であり,加工用リンゴは,生食用には出荷しにくいものを加工用と出荷したものである。これに対して,東部および中西部の生産者は,当初から加工市場を対象にして生食・加工兼用品種または加工用品種を栽培しており,ワシントン州に比べて加工用品種の生産量の割合が高かった(図2)。
7つの州における2007年における有機リンゴの生産量は,総計でも20.2万トン(生食用19.1万トン,加工用1.1万トン)で,リンゴの総生産量の約5%を占めるだけであった。有機リンゴ生産量のうち,ワシントン州が91%,カリフォルニアが8%を占め,東部および中西部での有機リンゴの生産量は合わせても全体の1%にすぎなかった。
ワシントン州は寒冷・乾燥気候で,気象的にリンゴ生産に有利だが,乾燥気候のために,病害虫が東部などの湿潤気候のように病害虫が蔓延しにくいために,合成農薬を使用しない有機栽培に有利となっている。
アメリカのリンゴ生産ではコドリンガ(coddling moth)の防除が大切である。コドリンガは,シンクイガの一種で,リンゴやモモなどにつく大害虫で,熟していないくだものの実や葉っぱに卵を産み,ふ化した幼虫は中身を食べる。日本以外の温帯気候地域に生息する。日本では法律により「輸入禁止対象病害虫」に指定されている。ワシントン州のような寒冷気候下では年間に1世代しかすごせないが,温暖気候下では2〜3世代を過ごすので,合成農薬がないと,甚大な被害が生じやすい。
また,スモモゾウムシはリンゴの若い実の表面をかじって傷をつけ,産卵し,幼虫が果実内部に穴を開け,未成熟果実が落下する場合もあり,さらに,晩夏から秋に成虫が成熟した果実をかじり,摂食部分に大きな傷やこぶを作って,大きな被害を与える。スモモゾウムシはロッキー山脈の東側に生息していて,東部や中西部に甚大な被害を与えているが,ワシントン州には生息していない。この点でもワシントン州が有利となっている。
その上,過去10年間にわたってワシントン州の研究センター,企業や個人が有機のリンゴ生産システムについて集中的に研究を行ない,有機のリンゴの味や外観を大幅に向上させてきた。こうした結果,ワシントン州の慣行および有機のリンゴ生産が,アメリカでぬきんでるようになった。
●リンゴ園の概要
A.経営期間
2007年において7つの州のリンゴ生産者は,慣行リンゴで平均19年間リンゴ園を経営していた。そして,有機リンゴで平均17年間経営し,有機としての認証機関は平均9年間であった。大部分の有機の生産者(63%)は有機認証をえる前に果樹園を慣行で5年間かそれ未満しか経営しておらず,慣行方法で20年超も経営していた生産者は一部(13%)にすぎなかった。
アメリカの多くの有機リンゴ生産者は慣行栽培と併存しながら,全面有機生産までゆっくりと移行してきた。しかし,2007年では調査した州の認証有機リンゴ生産者の大部分は全面的有機となり,有機リンゴ面積の16%だけが,慣行リンゴ生産と併存していた。
B.他の果樹との混合経営
2007年に調査した慣行および有機のリンゴ生産者の半分強はリンゴだけを栽培していたが,リンゴ生産者の約36%はリンゴに加えて1つまたは2つの別の果実または木の実を栽培していた。ミシガン,ノースカロライナ,ニューヨーク,ペンシルバニアではリンゴに加えてモモ,オレゴンではナシ,ワシントン州ではブドウを栽培しているケースが多かった。
C.品種
2007年に調査した7つの州を合わせると,慣行栽培で使われていたリンゴ品種は,レッドデリシャス22%>ゴールデンデリシャス14%>ガラ12%>ふじ11%>グラニースミス10%などであった。
有機栽培でも使われている品種は類似していたが,順位に違いがあり,ガラ22%>ふじ16%>レッドデリシャス14%>ゴールデンデリシャス11%>グラニースミス7%>ピンクレディ7%などであった。
このうち,レッドデリシャス,ガラ,ふじは生食用だが,ゴールデンデリシャス,グラニースミスは生食用と加工用の兼用種であり,有機栽培は生食用をターゲットにし,慣行栽培では生食用と加工用の双方をターゲットにしていることが品種からもうかがえる。
ちなみに,リンゴ品種が育成された国は,レッドデリシャスとゴールデンデリシャスがアメリカ,ふじが日本,ガラがニュージーランド,グラニースミスとピンクレディがオーストラリアである。
D.栽植密度と単収
慣行と有機の双方とも,矮性台木に接ぎ木した半矮性樹が全体の半分を占め,平均の栽植密度は1,100本/haであった。
調査した7つの州の慣行リンゴの平均単収は,気候的な条件もあって,州によってかなり異なり,単収が最も高いワシントン州の37 t/haから最も低いノースカロライナ州の10.1 t/haまでの幅がある。ちなみに2010年の日本のリンゴの平均単収は20.6 t/haなので,ワシントン州の単収の高さはぬきんでている。
慣行栽培と有機栽培の平均リンゴ単収は,ワシントン州で慣行の37.0 t/haに対して有機で30.3 t/ha,カリフォルニア州で慣行の31.4 t/haに対して有機で20.2 t/haであった。慣行を100としたときの有機の単収は,ワシントン州で82%,カリフォルニア州で64%であった。
E.有機認証料金
有機認証の料金は,認証面積からの販売額または認証面積数のいずれかに基づいて設定されている。2007年におけるリンゴ生産者が支払った平均認証費用は,エーカー当たり,ワシントン州とカリフォルニア州で30ドル(74ドル/ha),オレゴン州で約70ドル(173ドル/ha)であった。アメリカ農務省は2002年から全米コスト分担認証プログラムを施行し,有機生産者に認証料金の最大75%または750ドルまでを払い戻している。
F.価格プレミアム
有機リンゴは主に生食用として販売されている。2007年における調査した7州の生食用リンゴの平均価格は,有機で1.21ドル/kg,慣行で0.55ドル/kgで,有機の慣行に対する価格プレミアムは120%であった。
●有機栽培における病害虫管理用資材の使用
アメリカでは1996年に承認された「食品品質保護法」によって,EPA(環境保護庁)は食品中の残留農薬の新しい耐容基準を設定することが求められ,特に発ガン物質と分類されたカーバメート系,有機塩素系,有機リン系などの農薬の使用が厳しく規制された。これを受けて,慣行のリンゴ生産でもこれらの化学農薬の使用量が減らされるとともに,有機生産で使用の認められている資材の使用が増えている。そして,こうした化学合成農薬の使用規制強化が,有機栽培が増えた背景の1つとなっている。
2007年に調査した7つ州で,法律で有機での使用が承認された資材のうち,有機リンゴ面積の半分超で使用されたものは3つで,害虫防除用の園芸用機械油,病害防除用の多硫化カルシウムと生物農薬であった(表1)。その他には,土壌生物への蓄積を防止するという条件付で使用の認められているイオウ剤と銅剤の使用面積割合が高かった。なお,園芸用機械油,銅剤,イオウ剤,多硫化カルシウムは発ガン物質とはみなされず,EPAはこれらを食品中の残留農薬の耐容性基準の適用対象外とした。
●カオリン噴霧による害虫防除
表1において,有機リンゴ面積の約13%で害虫管理のためにカオリン粘土の噴霧が実施されていたことが注目される。
カオリンは,加工食品や歯磨きなどで凝固防止剤として長年使用されている食品添加物としても認められている鉱物である。農薬成分の分散や安定化のために,粘土を使用するケースは少なくないが,この方法では農薬成分は全くなく,カオリンだけを噴霧する。農務省農業研究局の研究所の研究者が噴霧器開発を行なった民間企業との共同研究によって,約10年前に害虫防除のために開発した手法である。カオリン噴霧についてはSlattery (2011)の報告書はあまり詳しくないので,T. Hinman and G. Ames (2011) Apples: Organic Production Guide. 38p. National Center for Appropriate Technology. IP020 (PDF Download) 有料 ($5.95). から若干補足する。
この方法では,カオリンの懸濁液をリンゴなどの果樹全体に噴霧する。水が蒸発すると,幹,枝,葉,果実の全ての表面が微小なカオリン粒子の薄いフィルムによって被覆される。カオリンフィルムはいくつかのメカニズムで有効であると考えられている。(1) カオリン被覆後に飛来した害虫にカオリン粒子が付着し,害虫は困惑してよそへ飛び去る,(2) カオリンが付着しなくても,害虫はカオリンに被覆された樹体や果実を食べたり産卵したりするのを嫌う,(3) 白く反射する樹体を宿主として認識しにくくなる,といったことが推定されている。
スモモゾウムシや第1世代のコドリンガを防除するには,花弁が落下したときから侵入が終わるまで,6〜7週にわたって毎週カオリンを噴霧し,風雨でカオリンフィルムがなくなった場合には,噴霧し直す。スモモゾウムシによって20〜30%の果実に被害がでたリンゴ園でカオリン噴霧を行なった区画では,被害が0.5〜1%に減少したなどの例がある。リンゴミバエを防除するために,全生育期間にわたってカオリンを噴霧する場合には,収穫した生食用果実に付着しているカオリンを拭き取るか洗浄して除く。
●有機栽培におけるその他の有害生物管理方法
慣行栽培ではこまめに圃場を監視しなくても,化学農薬の使用によって容易に有害生物を管理できる。しかし,有機栽培では丹念に圃場を観察して,有害生物発生の兆候を把握して,速やかに手をうつことが必要である。このため,有機面積の84%がこまめに監視されていた(表2)。そして,有害生物を検出する土壌や作物体の分析は30%だけであまり高い割合ではなかった。また,気象データの把握とその活用を行なっているのは,慣行栽培では87%で,有機栽培の68%よりも高かった。これは,慣行栽培では農薬散布のタイミングを決めるのに気象要素が重要なので,より高頻度で考慮されているためと理解されている。
慣行栽培では雑草が様々な化学除草剤で管理されているのに対して,有機栽培では他の方法が用いられ,なかでもリンゴ栽培面積の77%で樹間が耕耘されていたことが注目される(表2)。しかし,Hinman and Ames (2011)(前出)によると,耕耘は土壌表面に近い根を傷める。このため,耕耘とマルチ(草生栽培によるリビングマルチと,作物残渣,木質チップなどの植物遺体マルチ)を組み合わせているケースが多いとされている。表2の「土地被覆,物理的障害」の77%の多くは雑草抑制のためのマルチであると理解される。また,有機面積の26%で火炎銃が使用されていた。
その反面,病害虫防除の点では,病害虫の汚染源になるとして,「作物残渣,落ち葉,剪定枝の除去」が有機栽培面積の58%で行なわれていた。その上,病害虫防除では「フェロモンおよびおとり植物」が有機面積の81%,生物農薬が79%で使用されていた。また,有害生物管理のために,定期的灌漑,計画的排水,保持水処理といった水管理が実施され,その実施面積割合は,慣行よりも有機栽培で高かった。そのほか,抵抗性品種の使用,病害や雑草種子の伝播防止のための作業機の洗浄があった。
有益生物(昆虫,ネマトーダ,カビなど)の生物農薬の散布ないし放飼に加えて,土着の有益生物(フクロウ,コウモリ,テントウムシなど)の保護や生息地の維持も高い割合で実施されていた(表2)。
有機生産者は自分の経営体内の有機栽培面積と慣行栽培面積との間に緩衝帯を設け,隣接する慣行栽培の経営体との間に境界帯を維持することが要求されている。このため,緩衝帯や境界帯が慣行よりも有機面積ではるかに高い割合で維持されていた。
●有機栽培における養分管理
アメリカの肥料統計では,肥料施用面積割合が通常記載されている。2007年のリンゴ栽培に関する調査でも,3要素の施用面積割合が集約されている。慣行栽培では化学肥料および市販堆肥によって,窒素は栽培面積の約2/3(71%)に窒素,約1/3にリンとカリ(24%にリン,35%にカリ)が施用され,窒素に比べてリンやカリを施用した面積割合が小さかった。有機栽培でも,市販堆肥で3要素を施用した面積割合は慣行栽培と同程度で,窒素は栽培面積の約2/3(57%)に窒素,約1/3にリンとカリ(26%にリン,26%にカリ)であった。そして,非販売(自家製造)の堆肥および新鮮きゅう肥の施用は,有機栽培で堆肥が49%,きゅう肥が8%に施用していたのに対して,慣行栽培で堆肥が3%,新鮮きゅう肥が4%にすぎなかった。なお,新鮮きゅう肥の多くは家禽ふんであった。
なお,ここでの堆肥(compost)は,全米有機プログラム規則にしたがったもので,植物ないし動物起源の有機物を好気的分解が起きるように管理して温度を上昇させ,病原生物をできるだけ減らしつつ,土壌改良資材としての物理的および養分的性質を向上させるプロセスによって製造した生産物のことである(環境保全型農業レポート.No.167 アメリカが有機農業ハンドブック2010年秋版を刊行)。また,新鮮きゅう肥(manure)は,未堆肥化家畜排泄物などで,堆肥化してない家畜のふん,尿,その他の排泄物,ふん尿の付着した敷料のことである。有機栽培で新鮮きゅう肥の施用が少ないのは,人畜共通の病原生物による農産物の汚染を防止するために,全米有機プログラム規則によって,新鮮きゅう肥の施用が制限されているためである。すなわち,可食部分が土壌と接触している生産物を収穫の120日よりも前に施用する場合,または,可食部分が土壌と接触していない場合には収穫の90日よりも施用する場合を除き,新鮮きゅう肥を有機栽培で使用することが禁止されている。その場合には,作物生産で使用する前に堆肥化することを規定されている。
有機栽培では,養分状態の土壌診断が慣行栽培よりも高い頻度で実施されていた。報告書によると,2007年において,窒素診断は有機面積の86%,慣行面積の43%で実施され,リン+窒素の土壌診断は有機リンゴ面積の83%,慣行面積の31%で実施された。これらに加え,養分欠乏を診断する植物組織または葉の分析は,有機面積で71%と高く,慣行では28%にすぎなかった。土壌または栄養診断の結果に基づいて窒素を施用したのが,有機面積の76%,慣行面積の40%であった。作物コンサルタントの勧告に基づいて窒素施用決定がなされたのは,有機面積の67%,慣行面積の33%であった。このように有機栽培では土壌・栄養診断に基づいた施肥が慣行栽培でよりも多くの面積で実施されていた。
●終わりに
日本では、青森県の木村秋則さんが自然農法によって,特段の購入資材を使用しないでリンゴを生産し,大きな注目を集めている。まさにまだ奇跡であり,他者が追随できないでいる。そのメカニズムを解明して,再現可能にできることが望まれる。
アメリカのリンゴの有機栽培は,木村さんのような自然農法によるものではなく,法律で認められた適切な資材を使い,有害生物管理では土着の有益生物の保護・生息地保護を含めた総合的な有害生物管理(IPM)を行ない,養分管理では土壌診断や作物診断を積極的に行なったものであることが伺える。