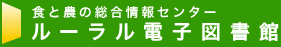No.179 チェルノブイリ原子力発電所事故20年後のIAEA報告書
2011年3月11日に起きた東日本大震災によって,福島県大熊町に所在する福島第一原子力発電所の原子炉が事故を起こした。この事故による環境影響や対策を正しく理解するには,25年前に起きたチェルノブイリ事故の報告書が参考になる。
●チェルノブイリ事故
1986年4月26日,旧ソ連のキエフから約100 km離れたチェルノブイリ原子力発電所の4号原子炉が事故を起こした。原子炉からは大量の放射線が飛び散り,核分裂を行ないながら放射線を出す放射性核種が10日間にわたって放出され,ヨーロッパの20万km2を超える面積が,3.7万 Bq/m2を超える137Cs(セシウム137)で汚染された。
注:Bq(ベクレル)は1秒間に放射線粒子を発射する能力。137Cs の場合はベータ線粒子(電子)を放出するが,137Cs からベータ線粒子が1秒間にm2当たり3.7万回発射されたという意味。
放射性核種が大気から降下して,土壌,植物や様々な物体の表面に蓄積することを沈着と呼ぶが,チェルノブイリ事故では,放射性核種の土壌沈着の分布図を作成する際に,測定しやすい137Cs を代表核種として選定した。そして,137Cs の土壌沈着量が3.7万 Bq/m2を超えた場合を,放射性核種による汚染土壌と判定した。この沈着量は,ヨーロッパでの自然沈着量の10倍に当たる。
旧ソ連は1991年12月に崩壊し,多数の国が独立した。チェルノブイリはウクライナ共和国に存在するが,ベラルーシ共和国やロシア連邦との国境に近く,この3か国にまたがる地域が特に強く汚染された。3.7万Bq/m2を超える137Cs で汚染された面積は,ヨーロッパ全体で20万km2を超えたが,その71%の14.6万km2をこの3か国が占めた(因みに日本の東北地方と関東地方を合わせた総面積は10.9万km2)。このうち,最も強く汚染された148万Bq/m2を超えたランクの面積は,0.31万km2に達した。そして,分布マップの凡例でみると,最高ランクの範囲は148万〜370万Bq/m2である。
ところで,2011年5月6日に,福島第一原子力発電所から80 kmの範囲の地表面への放射性物質の蓄積状況について,文部科学省およびアメリカエネルギー省航空機による航空機モニタリングの測定結果が公表された。その「別紙4」に,2011年4月29日現在の値に換算した137Cs の地表面への蓄積量の分布マップがあり,福島第一原子力発電所から北西の方向に蓄積量の高い区域が伸びている。その137Cs蓄積量の最高ランクの凡例の範囲は300万〜1470万Bq/m2で,強く汚染された面積はチェルノブイリよりも少ないものの,汚染濃度の最高ランクはチェルノブイリよりも高いことが注目される。
話をチュエルノブイリに戻そう。チェルノブイリでは,事故を起こした原子炉から半径30 km以内の強く汚染された地域は立入禁止区域となって,11万5千人の住民が強制的に避難させられ,全ての経済活動が禁止になった(その多くは,公式には今なお立入禁止)。そして,この事故当時に原子炉現場にいた作業者600人のうち,134人が高い被曝を受け,このうち30人の方が亡くなり,100人を超える人達が深刻な放射線被害を受けた。さらに2005年までに,6000人を超える子供や青年が甲状腺ガンを発症するなど,多数の人達に健康被害が生じた。
●チェルノブイリ事故に関する国際機関の報告書
原子力の平和利用において最大の被害をもたらしたチェルノブイリ事故については,複数の国際機関が報告書を作成しているが,その中で主だったものとして下記がある。
A.「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」の報告書
「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR) は,国連が問題にすべき原子力関連事件が生じた場合,その放射能の影響について科学的報告書を作成して国連総会に提出し,国連および加盟国が放射能リスクを評価して緩和対策を立てるのに役立つことを目的にして,1955年に設立された国連の委員会で,21か国で構成されている(日本も構成国の一つ)。
この委員会は,チェルノブイリ事故について,1988年以降,国連総会に報告書を不定期だが提出している(2008年のものが最新)。人間への健康影響が中心の報告書となっている。そのなかで2000年報告書の第2巻「影響」の付属書J「チェルノブイリ事故の被曝と影響」はしばしば引用されている。
B.「国際原子力機関」の報告書
「国際原子力機関」(International Atomic Energy Agency: IAEA) は原子力の平和利用のための国連付置機関である。IAEAはチェルノブイリ事故による健康影響と環境影響について,いろいろな国際機関や旧ソ連の深刻な影響を受けた3か国の専門家の強力を得て,2003年にチェルノブイリフォーラムを開催した。そして,チェルノブイリ事故による健康および環境についての影響と対策についてのこれまで20年間の調査や研究を集約して,今後必要な課題を整理する作業を開始した。
作業は「健康」と「環境」に分けて行なわれ,2つの報告書が2006年に刊行された。環境についての報告書は,IAEA (2006) Environmental Consequences of the Chernobyl Accident and Their Remediation: Twenty Years of Experience. Report of the Chernobyl Forum Expert Group ‘Environment’(STI/PUB/1239) 166p. 。
以下に,IAEA(2006)の環境についての報告書の概要を紹介する。
なお,健康についての報告書は,WHO「世界保健機構」から刊行されている。WHO (2006) Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes. Report of the UN Chernobyl Forum Expert Group “Health” 160p.
●原子力発電の基礎知識
一般の原子力発電は,質量235のウラン(ウラニウムともいう。235U )の核分裂反応で生ずるエネルギーを利用して水を沸騰させて,生じた蒸気によって発電を行なう。235U に中性子を当てると,いったん中性子を吸収して質量236のウラン(236U) を生ずるが,これは不安定で,放射線を出しながら,質量のより小さな2つ以上の原子に分裂し,2〜3個の中性子を放出する。この中性子が他の235U 原子をさらに分裂させて,連続的に核分裂反応が生じてゆく。核分裂反応の際は,放射線によるエネルギー放出よりもはるかに莫大なエネルギーが放出される。それは,分裂して生じた核の質量と中性子の総和は当初の235よりも小さく,減った質量分がエネルギーに直接変換されて,莫大なエネルギーが発生するからである。このエネルギーを使って蒸気発電を行なうのが原子力発電である。そして,発電用原子炉からは核分裂で生じた放射線や原子は外に漏れ出ないが,事故によって原子炉が損傷を受けると,放射線や原子が外に漏れ出てしまう。
235U が核分裂を行なうと,様々な核種が生ずる。生じた核種の中には,不安定で直ぐに核分裂を行なう放射性核種や,核分裂を行なわない安定核種も存在する。存在形態としては,多量の放射性ガス,濃厚なエアロゾル(微小粒子が高濃度に分散した大気),特定の元素だけの核種の微小な塊,燃料棒に含まれている235U 以外のいろいろな金属粒子と一緒になった塊などが存在する。
●健康に強く影響する放射性核種
原子炉事故で放出される放射性核種のなかで,人体に強く影響を及ぼす恐れが高いものは,量的に多く,放射線のエネルギーが比較的高く,半減期が短すぎないものなので,実際に問題になる放射性核種は限られている。事故直後では半減期8.04日の131I (ヨウ素131)がまず問題になる。半減期が20.8時間の133I (ヨウ素133)も放出されるが,半減期が短く,放射線放出が急速に減衰してしまうので,実際上は問題にならない。問題になるのは,半減期8.04日の131I である。
131I は,大気から,土壌に生えている作物の表面に沈着し,牧草や葉菜類のような表面積の大きな作物に多く沈着する。131I は特に乳幼児や青年の甲状腺に集積して,甲状腺ガンの発生率を高める。チェルノブイリの場合,131I によるこうしたリスクは,半減期が短いという理由で,最初の2か月間に限定された。
放射性ヨウ素とともに,放射性セシウムも大気から作物表面に沈着する。放射性セシウムのなかでは,半減期30.0年の137Cs と,半減期2.06年の134Csも重要となる。セシウムはカリウムに似た化学的特性を有しており,放射性セシウムの沈着した作物を食べた動物では,セシウムがカリウムと同様に細胞液の中に溶存状態で分布し,動物体の内部全体で,長期にわたって細胞に放射線を当てて被曝を起こすことになる。チェルノブイリの場合,作物体表面への放射線セシウムの沈着が問題になったのは,最初の2か月間であった。
大気からの作物体に沈着したセシウムの一部は作物体に吸収されるが,残りの大部分は土壌に沈着したり,作物残渣とともに土壌に還元されたりして,土壌に吸着される。大気からの沈着がなくなると,雨による作物体からの放射性核種の洗浄や自然崩壊などによって減少し,代わって根から吸収される放射性核種による放射能が問題になる。しかし,根からの放射性核種の吸収はあまり多くないので,作物体の放射能レベルは,大気からの沈着時に比べて大幅に低下する。
土壌から吸収される放射性核種のなかでは,まず137Cs と134Cs が問題になり,最初の数年間は半減期2.06年の134Cs も重要となる。そして,長期的には放射能性セシウム137Cs が重要になる。
ストロンチウムはカルシウムに類似した化学的性質を有するため,高濃度に存在すれば,骨に蓄積しやすい。しかし,90Sr(ストロンチウム90)は大きな粒子中に含まれているために,原子炉の近傍(100 km未満)で問題になった。一般に放射性ストロンチウムの降下量は少なく,生物濃縮も低いので,放射性セシウムに比べて人間の被曝には通常あまり関与しない。数100年から数1000年後に問題になると予測されるのは,放射性プルトニウム(Pu)同位体とアメリシウム(241Am )である。
●JCOの事故
ところで,1999年9月30日に,茨城県東海村に所在する住友金属鉱山の子会社の核燃料加工施設(株式会社ジェー・シー・オー(JCO))が起こした事故が思い出される。同社は,研究用高速増殖炉の燃料を加工するために,ウラン化合物粉末を溶解するのに,正規には「溶解塔」という装置を使用すべきところを,ステンレス製バケツを用いて作業を行なった。この過程で中性子などの放射線が大量に放射されて,死者2名と667名の被曝者が出た大事故であった。
この事故では多量の放射線は放出されたが,核分裂で生じた放射性核種がほとんど飛散しなかった。ただし,現場近くに存在した食塩のナトリウムや土壌中のマンガンなどが,放出された中性子の照射を受けて微量の放射性核種を生じた。しかし,それによる健康影響はほとんど問題なく,事故はもっぱら放出された多量の放射線によったユニークなケースであった。
こうした特殊ケースとは異なり,原子炉事故では,通常,放射線と放射性核種の双方が放出される。放射線だけなら,放射線の放出が終われば,影響は速やかに終息するのが通常である。しかし,放出された放射性核種が作物や土壌に付着していると,半減期の長いものの場合には,影響が長い間継続してしまう。
●事故後まもなく放射能汚染が問題になった食物
A.葉菜類とミルク
事故直後に,放射性ヨウ素や放射性セシウムが大気から作物表面に沈着した。これらの作物への沈着量は,作物の可食部位の重量当たりで表示すると,表面積の大きなホウレンソウのような葉菜類や牧草で多い。乳牛が放射性ヨウ素で汚染された牧草を食べると,消化された放射性ヨウ素が,腸からほぼ100%吸収され,ほぼ1日以内に甲状腺とミルクに移行する。人間の場合も基本的に同様で,131I は特に乳幼児や青年の甲状腺に集積して,甲状腺ガンの発生率を高める。チェルノブイリの場合,半減期が短い131I によるこうしたリスクは,最初の2か月間に限定された。
事故の起きた4月26日は,北ヨーロッパでは早春で,乳牛やヤギはまだ放牧地に出ていなかったため,ミルクの汚染はほとんど起きなかった。これに対して,旧ソ連の南部地域や,ドイツ,フランス,南部ヨーロッパでは,家畜が既に放牧されており,乳牛,ヤギ,羊のミルクの汚染が生じた。
草を食べて動物体内に取り込まれた放射性セシウムは,そのうちの60〜100%が吸収され,骨を除く,臓器や筋肉などのいろいろな組織全体(特に肝臓)やミルクに分布する。放射性セシウムは作物体にも蓄積されるが,動物体でより高い濃度で蓄積される。
農地などでは,放射性核種は物理的な自然崩壊によって減衰するだけでなく,作物体表面から風や雨によって除かれるので,牧草表面上での131I 放射能濃度の実効半減期(特定部位で放射能が自然崩壊に加えて,洗浄などの様々なプロセスによって,実際に減衰する際の半減期)は平均9日間,放射性セシウムで11日間であった。また,牛乳中の131I 放射能濃度の実効半減期は平均4〜5日間であった。また,137Cs が沈着した生草を食べた牛のミルクの137Cs の実効半減期は約2週間で,急速に137Cs 濃度が減少した。しかし,事故の起きた1986年の春〜夏に汚染牧草から乾草作り,それを9月から翌年5月中旬に給餌したために,この間にミルクの137Cs が高まったことが観察されている。
B.林産物
チェルノブイリ事故の後,森林で採取したキノコ,ベリー,狩猟鳥獣肉で高濃度の137Cs が検出されている事例が多く,しかも高い汚染レベルが長期間続いている。また,ヨーロッパの北極圏および亜北極圏において,コケ→トナカイ→人間系路で放射性セシウムが急速に移行することが確認されている。これらは半自然の森林生態系が備えている次の特性に起因していると理解されている。
(1) 森林では,耕地のように直ぐにセシウムを吸着する粘土鉱物の多い土層が表面に存在するのでなく,土壌表面に厚い有機物の層があってセシウムが吸着されにくいこと,
(2) 放射性セシウムが生物間でくり返し利用されて,持続的に循環していること,
(3) キノコの中には,土壌中の微量元素を吸収する能力の高い菌根菌などが多いこと,
(4) 後述するように,土壌中にカリウムが多いとセシウムの吸収が拮抗的に抑制されるが,森林土壌にはセシウムの吸収を抑制するほどのカリウムが存在していないこと,
などによると理解されている。林産物での汚染レベルは,多くの国でなお基準を超えており,この状態は,今後数10年は続くと予想されている。
因みに,日本で森林などから採取したキノコ,タケノコ,山菜などで高濃度の放射性セシウムが検出されたのも,その例といえよう。
C.魚
チェルノブイリは海から遠く離れているうえに,海では多量の水による希釈があるので,チェルノブイリ事故による海洋の放射能汚染は問題にならなかった。しかし,ベラルーシ共和国,ロシア連邦およびウクライナ共和国の,ミネラル養分が少なく河川による水の流入や流出が少ない一部の湖沼(閉鎖湖沼)では,魚の放射能汚染が問題になった。事故直後には寿命の短い131I などによる汚染も生じたはずだが,その影響についての記述は見当たらない。
問題核種として記述されているのは,生物濃縮もある放射性セシウムである。一部の閉鎖湖沼周辺に住んでいる人々では,魚を食べることが,全137Cs 摂取の主因となっており,今後かなりの期間残ると予測されている。そして,スカンディナビアやドイツのような遠く離れた一部の湖沼でも,魚中の濃度がかなり高まった。90Sr は一般に降下量が少なく,生物濃縮も低く,しかも,90Sr は食用となる筋肉でなく,魚の骨に蓄積するので,放射性セシウムに比べて人間の被曝にはあまり寄与してはいなかった。
●放射性核種の土壌中での移動
燃料棒は235U 以外にもいろいろな金属元素から構成されているが,原子炉事故で燃料棒が溶けるとともに,様々な大きさに破断されて大気に放出された。このとき,原子炉に近い場所ほど,大きな燃料粒子が土壌に沈着し,土壌中で時間とともにゆっくり溶解した。
A.土壌pH
土壌中の放射性核種が作物に吸収されるためには,金属の燃料粒子が溶けて,放射性核種がイオンになって土壌に放出される必要がある。燃料粒子の溶解は土壌pHによって大きく異なる。燃料粒子の50%が溶解するのに要した期間は,pH 4の土壌で約1年であったが,pH 7の土壌では14年も要した。したがって,酸性土壌では燃料粒子の大部分は既に溶解しているが,pHの高い土壌では,このプロセスは今日でも完了していない。中性土壌では燃料粒子から溶解された90Sr が現在も増加しつつあり,今後の10〜20年にわたってさらに増えると予測されている。原子炉からの距離が遠くなるほど,飛散する燃料粒子の大きさも小さくなり,土壌中で溶解しやすくなるし,単一の放射性核種化合物だけの微細粉末が沈着するようになる。
B.下方移動
土壌表面に沈着した放射性核種は,やがて土壌を下方移動する。その際,移動速度は土壌タイプや,放射性核種で異なる。
例えば,泥炭土のような有機質土壌では,137Cs の下方移動は非常に早い。他方,90Sr は有機質土壌で遅い。そして,90Sr は腐植含量の低い砂土,河川の氾濫原で,有機質が少なくて構造が形成されていない土壌(軽しょうな腐植質砂土),森林火災があった場所や有機質層が除去された土壌で,有機質土壌の場合よりずっと早い速度で下方移動する。こうした条件では,90Sr は水分の対流的な動きとともに地下水層にまで早い速度で移動していく。これに対して,腐植含量の低い砂土では,137Cs は粘土鉱物に固定されてその移動速度はずっと遅い。
例えば,原子炉から約150 km離れたベラルーシ共和国のゴメル地域の,有機物の少ない砂土における137Cs と90Sr の時間による深さ別分布の変化を調べた例では,事故1年後の1987年に,137Csは0〜5 cm層に80%超が存在し,6〜10 cm層に10%超,11〜15 cm層に数%が存在し,それよりも下には分布していなかった。2000年には,0〜5 cm層に40%超が存在し,6〜10 cm層に約40%,11〜15 cm層に約10%,16〜20 cm層に数パーセントが存在し,それ以下の層には存在しなかった。他方,90Sr は,事故1年後の分布は137Cs とほぼ同様であった。しかし,2000年には0〜5 cm層と6〜10 cm層に約30%ずつが存在し,11〜15 cm層に約20%,さらに,16〜20 cm層,21〜25 cm層,26〜30 cm層,31〜35 cm層に数%ずつが存在していた。
このように両核種ともかなり下方移動しているものの,放射性核種の大部分は植物の根域内にとどまっている。この結果から,大気からの沈着で汚染が起きた場では,放射性核種が地下水にまで移動するリスクは低いとされている。
なお,上述した放射性核種の土壌における垂直分布は耕起してない土壌の場合であって,土壌を耕起すれば,土壌耕起のタイプや農具によって異なるが,放射性核種が耕起した層全体にかなり均質に分布する。
●土壌から作物への放射性核種の移動
放射性核種による作物体の汚染は,当初は大気からの沈着に起因し,やがて,根による土壌からの吸収に起因することになる。チェルノブイリ事故後の経過をみると,事故の起きた1986年には作物体が大気から沈着した137Cs によって汚染されて,137Cs 含量が最も高かった。事故1年後の1987年には根からの吸収が作物体の主たる汚染源になったが,作物体の137Cs 含量は,土壌タイプによって異なるが,1/3から1/100に減少した。
土壌からの根による作物体への放射性核種の吸収には,土壌中の放射性核種の存在形態とその濃度,土壌タイプ,土壌の水分状態,土性,作物種,根からの放射性核種の吸収を拮抗的に阻害する元素(拮抗元素:放射性セシウムに対してはカリウムやアンモニウム,放射性ストロンチウムに対してはカルシウム)の濃度などによって異なる。特に強く影響するのが拮抗元素と粘土鉱物の多少である。
A.拮抗元素と粘土鉱物
結晶性粘土鉱物の表面はマイナスの電荷を帯びていて,セシウム,カリウム,アンモニウム,ストロンチウムやカルシウムなどの陽イオンを,その表面に電気的に保持する。表面に保持された陽イオンは,土壌溶液中の他の陽イオンと交換されて,土壌溶液に溶け出て根に吸収される。そして,結晶性粘土鉱物は基本単位が何層にも重なった結晶だが,基本単位の間に薄い水の層を介在させているものもある。この水層にイオン状態のセシウム,カリウムやアンモニウムの一部が入りこんで,固定されて出られなくなる。この固定された陽イオンは土壌溶液に容易には放出されず,作物根に利用されなくなってしまう。
このため,養分含量が低くて,拮抗元素のカリウムやアンモニウムが少なく,粘土鉱物がなくて,セシウムを固定する能力がなく,有機物の多い泥炭土では,大気から沈着したセシウムが根に吸収されやすい。そして,養分含量が高くて拮抗元素が多く,粘土鉱物含量が高い土壌では,根に吸収されるセシウムが少なくなる。
ストロンチウムは大きすぎて,結晶性粘土鉱物の基本単位間の水の層には入り込めず,土壌には固定されない。そのため,土壌の粘土鉱物の多少が,ストロンチウムの根による吸収に影響することはない。カルシウムも同様である。このため,主に拮抗元素のカルシウムの多少が,根による土壌中からのストロンチウムの吸収に影響することになる。
B.放射性元素の移行係数
作物体の放射能濃度を土壌中の放射性核種の放射能濃度で除した値を,放射性元素の「移行係数」と呼ぶ。137Cs の移行係数が最も高いのは沼沢地の泥炭土だが,砂土では数十分の1ないし数百分の1に下がり,肥沃な耕地土壌では数千分の1に下がる。ヨーロッパの国の多くでは,泥炭土は自然草地として反芻家畜の放牧や乾草生産に使用されているので,泥炭土からの放射性セシウムの吸収量が多いことが,チェルノブイリ事故後に問題になった。
砂土,砂壌土および埴壌土のポドソール土壌で栽培した冬ライムギの,子実への137Cs の移行係数を土壌中のカリウム含量との関係で調べた結果を見ると,カリウム含量が80 mg K/kg以下の土壌について,粘土鉱物の最も少ない砂土での移行係数を100とすると,粘土鉱物含量が多くなるにつれて移行係数が小さくなり,砂壌土で約75,埴壌土で約55となった。そして,各タイプの土壌について,カリウム含量が80 mg K/kg以下のときの移行係数を100とすると,81〜140 mg K/kgで30〜33,141〜200 mg K/kgで22〜24,201〜300 mg K/kgで20〜22,300 mg K/kg超で15〜17となり,カリウムの存在量が多いほど移行係数が小さくなった。このことから,後述するように,放射性セシウムの作物吸収量を抑制するために,カリ肥料の施用が実施されている。
ただし,日本の耕地土壌ではカリウムの過剰蓄積が進行しており,小原洋・中井信 (2003)(農耕地土壌の交換性塩基類の全国変動.日本土壌肥料学会誌.74: 615-622)によると,1994〜97年に行なわれた全国的な土壌調査に基づくと,交換性カリウムの平均濃度は,水田で215 mg K/kg,牧草地で293 mg K/kg,他の普通畑,野菜畑,樹園地,茶園,施設の土壌はいずれも300 mg K/kgを超えていた。このことからすると,日本の耕地土壌でカリウムの施用による放射性セシウムの吸収抑制効果はチェルノブイリ事故の影響を受けた3か国ほどは期待できないことも考えられる。
●集団農場と自留地農場
事故の起きた時点における旧ソ連の食料生産は,集団農場と自留地農場の2つでなされていた。その形態は,基本的には今でも続いている。
集団農場は,生産力を向上させるために,耕耘と施肥を行ないつつ,輪作を行なっている。これに対して,伝統的自留地農場は小規模で,化学肥料を施用することは滅多になく,1頭ないし多くても数頭の乳牛を有して,主に自家消費用に牛乳を生産し,作物収量向上のために乳牛ふん尿を多く使用している。そして,集団農場ではアンモニウム肥料やカリ肥料などの拮抗元素の施用といった牧草の137Cs 吸収抑制対策が実施されたが,自留地農場は後回しにされた。なお,自留地農場の放牧は,当初は集団農場の使用しない限界農地を利用したものに限られていたが,現在ではより質の良い放牧地も一部使用している。
事故後の牛乳汚染についての注意事項の連絡と緩和対策についてみると,集団農場には事故発生後すみやかに連絡が届き,緩和対策が数日後から実施されたが,自留地農場でこの時点で対策を実施されたのはごく一部にすぎず,対策が実施されたのは1990年になってからであった。こうした事情を反映して,ウクライナ共和国のロブノ地域における牛乳の137Cs 濃度は,集団農場に比べて自留地農場で高く推移した。
●事故後初期段階における緩和対策
A.旧ソ連
1986年4月26日に事故が起きたが,その周辺での主力農業は家畜生産であった。このため,5月2〜5日から,半径30 km以内の強く汚染された地域は立入禁止区域に指定され,約5万頭の牛,1万3000頭の豚,3300頭のヒツジ,700頭のウマが,人々とともに避難した。しかし,避難した動物用の飼料が不足し,かつ,移動した土地での多頭数の動物の管理が難しかったため,避難した動物の多くも屠殺された。また,避難後にも立入禁止区域内に2万頭を超える猫や犬を含めた農業動物や愛玩動物が残り,殺されて埋葬された。1986年5月〜7月に屠殺された動物の総数は,合わせて牛9万5500頭,豚2万3000頭に達した。
事故後の最初の数週間に旧ソ連で実施された食品の安全性確保対策の主眼は,131I のミルクの汚染を下げ,汚染されたミルクがフードチェーンに入るのを防止することであった。このために,下記の諸点が集団農場と地方自治体に指示された(自留地農場には伝えられず)。
(a) 家畜を放牧から屋内飼養に切り替えて,汚染された放牧地の牧草を排除して,汚染されていない「クリーン飼料」を給餌する。
(b) 加工プラントにおいて原乳の放射能をモニタリングし,131I の放射能が3,700 Bq/Lを超えたミルクを排除する。
(c) 排除されたミルクは,貯蔵可能なコンデンスミルク,粉ミルク,チーズやバターに加工する。
1986年5〜7月に放射能調査が実施され,ベラルーシ共和国,ロシア連邦とウクライナ共和国でそれぞれ13万ha,1.73万ha,5.7万haの農地が,経済利用から除外された。
1986年6月からは,137Cs の農産物への移行削減をねらった下記の緩和対策が実施された。
(1) 家畜には屠殺前1.5か月間クリーン飼料を給餌しなければならないが,137Cs の土壌汚染レベルが555 kBq/m2を超える地域では牛の屠殺を禁止する。
(2) 作物生産で通常実施されているいくつかの作業過程を省略し,汚染された粉塵の飛散とそれによる外部被曝を最小にする。
(3) 汚染されたふん尿の肥料使用を制限する。
(4) 乾草の代わりにトウモロコシでサイレージを製造する。
(5) 自留地農場で生産されたミルクの消費を制限する。
(6) 農産物の放射能モニタリングを義務化する。
(7) ミルクの加工を義務化する。
B.西欧諸国
旧ソ連や東欧諸国を除く西欧諸国も,緩和対策を行なった。その一部を紹介する。
(1) スウェーデン
スウェーデンは,旧ソ連諸国以外では最も高いレベルの沈着を受けた。同国は輸入および国産の食物中の131I と137Cs について基準値を課すと同時に,下記の対応策を講じた。
(a) 131I で10 kBq/m2,放射性セシウムで3 kBq/m2を超える沈着を受けた放牧地に牛を入れない。
(b) 葉菜類は生のまま食さず,他の生鮮野菜は水洗する。
(c) 下水汚泥は肥料として土壌に施用しない。
(d) 土壌を深耕する。
(e) 牧草は高い位置で刈りとる(高刈り)。
(2) ノルウェー
圃場の作物を収穫後にモニタリングし,放射性セシウムが600 Bq/kgを超える作物は廃棄し,プラウで埋め込んだ。6月に収穫した乾草やサイレージをモニターし,ガイドラインを超えた放射能濃度は飼料として使用しなかった。
(3) ドイツ
バイエルンで一部のミルクが食品加工プラントに運ばれて,粉ミルクに変換された。この粉ミルクは豚の飼料として使用される予定であったが,放射性セシウム濃度が高いために実施されなかった。
(4) イギリス
イギリスでは狩猟で得たアカライチョウの消費が禁止され,汚染された丘陵地のヒツジの移動と屠殺に制限が課せられた。
●後期段階における農産物の汚染状況の推移
事故後1年目の1987年からは,ジャガイモや根菜類は十分に低い放射性セシウムレベルで生産され,1991年までに最も強く影響を受けた3か国全てで,370 Bq/kgを超える放射性セシウムを有していた穀物は0.1%未満だけになった。そして,高い放射性セシウム濃度が観察された農産物は畜産物だけになり,ミルクと肉の137Cs 濃度を下げるのが集約農業での課題となった。最も難しい問題は,基準に合致したミルクの生産であった。
後述する抜本的対策の実施によって,例えばロシア連邦では,137Cs 含量基準を超えたミルクや肉の生産量が1986年から1996年に向かって急激に減少した。しかし,旧ソ連が1991年12月に崩壊し,1990年代中頃には財政的制約が厳しくなって,緩和対策の実施が劇的に減った。そのため畜産物の放射能濃度が増えたが,基準以下のレベルを維持できている。
●集約農業での緩和対策
A.土壌処理
農業生産が許された放射能汚染地帯では,放射性セシウム(および放射性ストロンチウム)について,土壌から作物への吸収を減らすための土壌処理がなされた。作業としては,
(1) 耕耘
作物根が大部分の養分を吸収することになる汚染された上層土壌を,混和して希釈することが目的で,深耕や浅耕が大面積で実施された。
(2) 窒素,リン,カリウム肥料と石灰の施用
化学肥料の施用は作物生産量を増やし,それによって作物体中の放射能を希釈することと,拮抗元素を施用して,放射性セシウムやストロンチウムの吸収を減らすことが目的。
(3) 再播種
生産物の放射能が基準を超える懸念がある場合には,放射性核種の吸収能の低い作物を再播種する。
これらの作業を全て含んだ土壌改良は,一般に抜本的改良と呼ばれた。また,石灰だけを施用した場合や,化学肥料を増肥料しただけの場合もあった。
1986〜1990年にロシア連邦で,抜本的改良が実施された面積は約10万ha,化学肥料(カリは平均年間約60 kg K2O/haの増肥)を増肥しただけの面積が約1800 ha,石灰だけを施用した面積は約270万haだった。肥料や石灰の施用は一回行なうだけでなく,経時的にくり返すことが必要だが,1991年に旧ソ連が崩壊して経済的事情が悪化して,それまでの施用量を維持することができなくなって,これらの実施面積が減少した。このため,いったん減少した農産物の放射性セシウム濃度が再び上昇した。
B.作物種による放射性セシウムの吸収量の違い
ベラルーシ共和国でのデータによると,エンドウの137Cs 吸収量を100とすると,ダイコン約60,キュウリ約55,食用ビート約42,インゲン約40,ジャガイモ約38,トマト約30,キャベツ約20,ニンジン約17といった違いが報告されている(筆者注:数値はグラフから読み取ったもの)。また,放射性セシウムを蓄積する飼料作物として,エンドウ以外にもルーピン,ソバやクローバがあり,これらの栽培は,完全ないし部分的に排除された。
C.ナタネの栽培
ベラルーシ共和国では,食用油と家畜飼料用の蛋白質粕という2つの産物を生産することを目的にして,ナタネが汚染地域で栽培されている。いろいろな品種のナタネが栽培され,他の品種よりも137Cs や90Sr の吸収量が1/3〜1/2しかない品種が栽培されている。そして,子実の放射性セシウムや放射性ストロンチウムの濃度をさらに半分にするために,肥料の追加(6 t/haの石灰と,窒素90−リン酸90−カリ180 kg/haを施用)がなされている。そうした対策によって,ナタネ油と粕に残留する放射性セシウムと放射性ストロンチウムは,双方とも無視できるほどであった。
ナタネ油の製造は,汚染農地を活用した経済活性化方策であり,農業者と加工業の双方に利益をもたらすとされている。過去10年間にナタネ栽培面積は4倍に増えて,2万2000 haとなった。しかし,加工処理能力が生産拡大のネックになっている。
因みに,このナタネ栽培は放射性核種の吸収量の少ない品種を使用しており,汚染土壌の浄化にそれほど大きな効果があるとは思えない。
D.クリーン給餌
汚染された家畜に,屠殺前または搾乳前の適当な期間に,汚染されていない飼料ないし放牧牧草を供給すること(クリーン給餌)は,各核種の家畜における実効半減期にしたがった速度で,肉やミルク中の放射性核種の汚染を効果的に減らすことができる。放射性セシウムの実効半減期は数日なので,ミルク中の放射性セシウム濃度はクリーン飼料の給餌により急速に減少する。肉では筋肉中の実効半減期がより長いので,減少にはより長い期間がかかる。
クリーン給餌は,旧ソ連と西ヨーロッパの双方の国々でチェルノブイリ事故後に畜産物に対する最も重要な対策の一つとして実施されている。クリーン給餌は旧ソ連のいずれの3か国でも肉生産のために,家畜の体のモニタリングと結合させて常套手段として実施されており,家畜生体が基準を超えていれば,家畜はさらにクリーン給餌を続けるために農場に戻すことが可能である。
E.セシウム結合剤の投与
ヘキサシアノ鉄 (II) 酸塩化合物(M14[Fe(CN)6])(通称プルシャンブルー)は,効果の高い放射性セシウム結合剤である。これを搾乳用家畜(牛,ヒツジ,ヤギ)や肉用家畜の餌に添加すると,放射性セシウムの腸での吸収を減らして,ミルクや肉への移行を最大で1/10に削減できる。この毒性は低く,安全である。いろいろな国で,効果が高く,安価でローカルに利用できるいろいろな形態の製剤が開発されている。プルシャンブルー投与は,抜本的改良に適した採草地がない集落で特に便利である。
F.緩和対策の効果(要約)
旧ソ連の最も強く影響を受けた3か国で実施された各種対策によって得られた,農産物中の放射性セシウムと放射性ストロンチウムの削減係数(緩和対策実施前と後の放射性核種の濃度の比率)をまとめたものを表1に示す。
この表で削減係数が2.5とあれば,当該対策の実施によって,放射性核種の濃度が2.5分の1に減少したことを意味する。
●立入禁止区域の現状と将来
立入禁止区域の扱い方は旧ソ連の3か国で異なっている。
A.ベラルーシ共和国
事故の起きた1986年の立入禁止区域は21万5000 haで,そこに居住していた人達は避難し,全ての生産活動が禁止された。立入禁止区域の大部分は,長寿命の放射性核種による汚染のために,100年以内に経済生産に戻すことができない。許可されているのは,放射線安全性確保に関連した活動,つまり,森林火災の消火,放射性物質の移動防止,環境保護,科学研究と実験作業が許可されているだけである。1988年に政府の布告によって立入禁止区域の大部分が国立の放射線生態学保全地域に指定され,立入禁止となっている。ただし,高齢者を中心とした少数の人達が,無許可で当該地域に居住している。
1990年代初期に,総面積45万haの再避難区域が追加指定された。この再避難区域には,高濃度の放射性核種で汚染された26万5000 haの農地があり,農業利用から除外された。再避難区域の残りの農地は,将来的には農業利用が可能になると考えられている。しかし,そうした農地の排水システムや道路が劣化し,排水がないために地下水位が徐々に上昇し,植物遷移によって永年性雑草や灌木が増えている。この再避難区域では,立入禁止区域と異なり,道路,送電線の維持活動など,限定された立入が認められている。
ベラルーシでは,可能なら土地を農業利用に戻すことが重要と考えられており,2004年現在で1万6100 haが農地に戻された。これらの土地はいずれも定住集落のごく近くで,緩和対策が実施されている。ただし,経済事情が厳しいため,採草地の抜本的改良,プルシャンブルーの牛への投与,石灰施用と施肥に限定されている。しかし,復元農地での農業を軌道に乗せるには,破壊されたインフラ,高い生産コスト,農産物に対する市場の低い需要の改善が不可欠であり,そのためには,国の経済状態の全般的改善が必要である。
B.ウクライナ共和国
チェルノブイリ発電所近傍の立入禁止区域外に,後日,10万1285 haの再避難区域が設定された。ウクライナ共和国はこの再避難区域について,下記の条件が満たされれば,定住や経済利用の再開を許可している。
(a) 放射線医学的条件:地域産物および当該地域の個人や集団の被曝量の減少(当該地域に制限なしに定住できるには,年間被曝量が1ミリシーベルトを超えないこと)
(b) 経済的条件:地域産物の市場価値の向上
(c) 社会および心理学的条件:当該緩和対策に対する市民の意見
再避難区域の放棄地面積は10万1285 haで,そのうち,2004年時点で放射線医学的条件を満たした土地は70%超と判定されたが,3つの条件を同時に満たすと判定された土地は1万5785 haであった。1998〜2000年に,このうちの6,095 haは利用再開が許可された。しかし,残りの面積は2001〜2006年に許可する予定であったが,経済事情の悪化のために許可が実施されなかった。
立入禁止区域では,制限になっている放射性核種は現在では137Cs よりは90Sr である。放射線医学的条件だけなら,立入禁止区域の南西部分は利用可能である。しかし,立入禁止区域の利用許可には法的論拠がないこと,インフラ整備が完備できないこと,経済および社会心理学的要因から,再利用が妨げられている。
ウクライナ共和国では経済の衰えから,農業的生産力の高い放射能被害を受けていない農地の放棄面積も増えており,放棄農地を生産に戻すニーズが減っている側面もある。
C.ロシア連邦
1987〜89年に高度に汚染された放棄地の大部分で緩和対策が実施された。しかし,部分的にも成功したのは一部だけで,農地は徐々に放棄され,1990年代には経済事情の悪化から緩和対策の実施強度が減らされた。全体で約1万1000 haが1995年までに農業利用に戻された。農業利用に戻す決定は,ロシアの農産物品質基準を含む放射線安全性基準に基づいて,汚染圃場ごとに個々になされた。
1995年と2004年の間にそれ以上の放棄地の復元はなかった。公式には放棄されている土地に,一部の地元民が非公式に定住して農業非公式には利用しているが,緩和対策の恩恵を受けていない。
●おわりに
IAEAの報告書は,チェルノブイリ事故による放射能汚染の状況に加えて,環境を都市環境,農業環境,森林環境,水環境に分けて,それぞれの環境における放射能汚染の状況,放射性核種の移動や生物濃縮,さらに各環境の汚染緩和対策について,160ページにわたって図や地図を多く引用しながら,旧ソ連とヨーロッパでなされた研究をまとめて述べている。そして,チェルノブイリ事故の影響の推移をモニタリングし,影響を緩和するために今後必要な行政的および科学・技術的課題を整理し,IAEA加盟国に対して,今後考慮し行なうべき課題を勧告している。
チェルノブイリ事故で得られた知見は,今回の福島第一原子力発電所事故による農業対策に役立つはずである。是非一読をお勧めする。
また,原子放射線の影響に関する国連科学委員会やIAEAがチェルノブイリ事故について,事故後25年を経過しても報告書をまとめているように,福島第一原子力発電所事故についても,世界各国の参考に供するために,事故や汚染の実態,人体や環境への影響,緩和対策についての調査や研究をまとめることが当然予測される。その際には,日本の調査や研究が中心になるであろう。今後,世界各国の参考になるような,きちんとしたデータ集積や研究を長期にわたって行ない,チェルノブイリでは得られなかった新しい技術や知見を世界に提供すること日本に課せられるであろう。