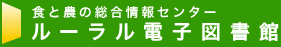No.86 有機農業用家畜ふん堆肥の品質基準の必要性
●有機畜産と有機栽培の谷間
有機飼料の日本農林規格 で,有機畜産で使用できる飼料は,原則として,(1)有機農産物,(2)有機加工食品,(3)有機乳,(4)有機飼料,(5)有機飼料用農産物,(6)食塩,(7)水,(8)石灰石等(化学的処理を行なっていない石灰石,貝化石,ドロマイト,リン鉱石,ケイソウ土で,化学合成した炭酸カルシウム,炭酸マグネシウム,リン酸二石灰,リン酸三石灰,ケイ酸を添加していないもの),(9)天然物質または天然物質に由来して化学的処理の行われていない飼料添加物(抗生物質および組換えDNA技術を用いて生産されたものを除く)に限定されている。
このように有機畜産では,化学合成した銅・亜鉛化合物,リン酸化合物,抗生物質および遺伝子組換え作物体由来飼料の使用を禁止している。しかし,日本では有機畜産がほとんど実施されていないため,「有機の家畜ふん堆肥」がほとんどない。
なお,家畜ふん堆肥に限らず,遺伝子組換え体由来の堆肥材料が混入しているケースが多々あると考えられる。しかし,遺伝子組換え体に由来した材料か否かのチェックが実際には難しいため,「有機農産物及び有機加工食品のJAS規格のQ&A」で,遺伝子組換え体の混入した材料から製造した堆肥でも,当分の間(2010年に予定されている有機JASの次の改訂まで),有機農業で使用できることになっている。
●畜産主体のEUの有機農業
2005年におけるEU(25)の慣行経営体を含めた全経営体の平均農地面積は16.0 haだが,有機経営体の平均農地面積は38.7 haで,慣行経営体よりも大きい(EUROSTAT, 2007b)。
有機農業の認定を受けた農地面積に占める作目別割合をみると,EUの平均で,その2/3が飼料作物(放牧草地,採草地と1年生飼料作物)となっている(図1)。採草地の牧草と1年生飼料作物は,複合経営体では耕種作物と輪作されていると考えられる。また,労働集約的な野菜の栽培面積はわずか1%に過ぎないことが注目される。EUのように有機の飼料作物生産とそれを利用した有機の家畜生産が多ければ,「有機の家畜ふん尿」を有機栽培に利用することができる。
●コーデックスのガイドラインと日本農林規格
EUの有機農業基準やコーデックスのガイドラインは,土壌肥沃度を輪作や有機飼養の家畜に由来する家畜ふん尿利用によって維持・増進することを基本とし,抗生物質などの飼料添加物に大きく依存した「工業的に」飼養された家畜からの堆肥を認めていない(表1)(Codex Alimentarius Commission (1999) Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods.)。
「有機農産物の日本農林規格」は,表1に該当する部分を表2のように規定している。コーデックスやEUの規定に比べると抽象的で,これは輪作や有機畜産によって生産された家畜ふん堆肥といった表現を使わないように工夫した結果と推察される。そして,家畜ふん堆肥については,家畜および家禽の排泄物に由来して,堆肥の製造工程に化学合成物質を添加していないことだけを規制し,「工業的農業」に由来する家畜ふん尿については論及していない。
慣行の家畜ふん尿には,有機農業で禁止された化学物質が,餌から持ち込まれて含まれている。コーデックスやEUの規定は,有機農業で禁止された物質をある程度含んでいる家畜ふん堆肥を使用することを認め,多量に含んでいるケースを排除している。しかし,日本の規定では,餌にどれだけ多量に添加しようとも,ふん尿を堆肥化する過程で添加したのでなければ,有機農業で使用することを認めている。この点は国際的に問題になりうる。つまり,有機農産物の国際取引をするとき,コーデックスのガイドラインが共通の要件になっているからである。日本の規格は家畜ふん堆肥に関してはコーデックスのガイドライン以下なので,今のままの規格では,日本の有機農産物を輸出しようとした際,相手国から日本の規格は国際水準に達していないから,有機農産物として輸入できないといわれても反論できないことになる。
☆「有機畜産」「JAS(日本農林規格)」に関する記事を「農業技術大系」から探す → 検索
●慣行の家畜ふん堆肥の抱えている問題点
(1)重金属
家畜の成長には銅や亜鉛が必要だが,トウモロコシなどの飼料原料に含まれている量だけでは不足するので,銅や亜鉛が添加されている。しかし,実際に流通している配合飼料には,最低必要量の何倍もの多量の銅や亜鉛が添加されているケースが少なくない。こうした飼料への銅と亜鉛の過剰添加を反映して,神奈川県で流通している家畜ふん堆肥には,どの畜種の堆肥にも異常なまでに高濃度の銅や亜鉛が含まれているケースが存在し,平均値では豚ぷん堆肥に他の畜種の堆肥よりも高い濃度の銅と亜鉛含量が含まれていることが確認されている(折原健太郎・上山紀代美・藤原俊六郎 (2002) 家畜ふん堆肥の重金属含有量の特性.日本土壌肥料学雑誌.73: 403-409)(表3)。
日本は農地土壌の重金属類汚染について,田に限って,カドミウム,銅,ヒ素の3種類を規制しているだけである。これはかつて,鉱山から水系を経て重金属類が流入して水田土壌を汚染したケースが多いことを踏まえた規制と理解できる。しかし,今日では汚泥,リン酸肥料,家畜ふん堆肥などの多量施用によって重金属濃度が高まっている畑土壌が少なくない。EUが農地土壌について銅と亜鉛を含めてより多くの重金属について上限値を定めているのに比べて,日本の規制は遅れている。EUは農地に施用可能な汚泥中の重金属の上限量を銅で12 kg/ha,亜鉛で30 kg/ha・年としている(EU (1986) Council Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture. )。
このEUの施用上限量を踏まえて神奈川県の家畜ふん堆肥で計算すると,濃度の高い家畜ふん堆肥では農家が実際に施用している堆肥量で,EUにおける汚泥での施用可能上限値に達してしまう(表3)。日本の法律では畑の銅と,水田と畑の亜鉛について規制されていないから,何ら考慮しなくて良いとするのは科学的でない。家畜ふん堆肥を長期連用して問題になるような銅や亜鉛の土壌蓄積が生じないように,家畜ふん堆肥の銅と亜鉛の濃度と施用量の上限値を明示して,上限値以下の濃度と量の家畜ふん堆肥を有機農業では施用するようにガイドラインを作ることが望まれる。
☆「重金属」の問題に関する記事を「農業技術大系」から探す → 検索
(2)リン酸
家畜ふん堆肥中の三要素について,化学肥料と同様に作物に吸収可能な養分量(化学肥料相当養分量)の組成をみると,いずれの畜種の堆肥でも,窒素に対してリン酸やカリが過剰である(表4)。このため,家畜ふん堆肥を軸にした施肥を行なって,土壌のリン酸レベルが過剰なまでになったケースも少なくない。
作物生育にとって窒素が過剰になるほどに家畜ふん堆肥を施用すれば,余剰な窒素から生じた硝酸が水質汚染を起こす。しかし,化学肥料相当窒素が適正量になるように,家畜ふん堆肥の施用量を調節したとしても,リン酸とカリの供給が過剰になる。従来,リン酸は土壌に吸着され,農地から排出されないと考えられていた。しかし,激しい豪雨の際に土壌粒子ごと表面流去されたリン酸が,地表水の富栄養化を助長し,アオコの発生の原因になる。また,可給態リン酸濃度が異常なほど高くなった土壌では,地下水にもリン酸が溶脱され,やがて地表水のリン酸濃度上昇を引き起こすことになる。
このため,家畜ふん堆肥だけを施用するのでなく,植物質堆肥や有機質肥料と組み合わせて,三要素のバランスのとれた施肥を行なうことが必要である。
ところで,リン酸肥料の過剰施用によって今日では日本の耕地土壌の可給態リン酸が過剰になったケースが多いとはいえ,日本の土壌は元来リン酸不足であった。化学肥料を排除して,植物質堆肥だけで有機農業を続けていると,化学肥料施用で溜まった土壌の可給態リン酸レベルが低下して,後には,再びリン酸欠乏で作物収量が低く抑制されることが懸念される。そうした事態を避けるためにも,家畜ふん堆肥をリン酸源として活用することが大切である。
(3)抗生物質
抗生物質投与によって,家畜の腸内でクロストリジウム症やコクシジウム症などを起こす有害細菌と有害物質産生が減少し,またこれらによって腸管内壁が薄くなり栄養吸収率が高くなり,成長促進の効果があるとされている。こうした飼料の栄養成分の有効利用促進のために,日本では19種類の抗生物質が飼料添加物として認められ,抗生物質の総使用量の約10%が飼料添加物として利用されている。
抗生物質添加飼料を給餌した家畜から排出された抗生物質が,堆肥化過程を経ても残っている可能性が懸念されている。しかし,5年間に調べた総計220の家畜ふん堆肥サンプルからは抗生物質が全く検出されなかった(畜産環境整備機構 (2005) 堆肥の品質実態調査報告書.全102頁)。このことから,抗生物質自体の残留はあまり懸念する必要はないと考えられる。
むしろ,堆肥を介した抗生物質耐性菌の蔓延が懸念される。環境保全型農業レポート.No.16 「家畜ふん堆肥中の抗生物質耐性菌」に紹介したように,自然界では微生物がお互いの競争に打ち勝つために,一部の微生物が抗生物質を生産する能力を獲得しており,それに対抗する抗生物質耐性菌も生存している。このため,人為の影響のない森林土壌にも抗生物質耐性菌が生存している。しかし,抗生物質を添加した飼料で飼養した家畜ふんと,その家畜ふん堆肥を連用した土壌には,院内感染で問題になっているアンピシリン,バンコマイシン,カナマイシン,クロラムフェニコール,リファンピシン,テトラサイクリンといった複数の抗生物質に耐性な多剤耐性菌が,森林土壌や家畜ふん堆肥無施用土壌よりも増えている。しかも,これら6種類の全ての抗生物質に耐性な細菌も少なからず検出されている。
土壌中の多剤耐性菌が作物を経て人体に侵入している可能性は今後検討すべき問題として残されているが,多剤耐性菌をできるだけ殺した家畜ふん堆肥を使ったほうが安心できる。屋内堆積で70〜80℃の高熱を発生させながら製造した鶏ふん堆肥では,アンピシリンを除く抗生物質に対する耐性細菌がほぼ完全に消滅していたことから,しっかり発熱する堆肥化が大切と推定される。このことから有機農業ではせめて多剤耐性菌があるレベル以下の家畜ふん堆肥を使うといったガイドラインが望まれる。
☆「抗生物質耐性菌」「病原菌汚染」に関する記事を「農業技術大系」から探す → 検索
●食の安全と環境の保全を担保する有機農業に向けた努力
有機畜産がない日本で,慣行の家畜ふん堆肥を排除するのは非現実的である。だが,慣行の家畜ふん堆肥を有機農業で無制限に受け入れられるというのは納得できない。化学肥料は危険で,有機物なら何でもどれだけ施用しても安全だという間違えた神話に依存した有機農業から,食の安全と環境の保全を担保できる有機農業へと脱皮する視点から,有機農業で使用可能な家畜ふん堆肥の品質基準を定める努力を重ねてほしいものである。