西尾道徳「環境保全型農業レポート」
| ◆2005年1月8日号 | 記事一覧 |
1.南九州における環境保全的な畑作技術と環境保全コストの負担
●問題の背景
南九州の畑作地帯では,かつてカンショ,オカボ,ダイズ,ムギ類やナタネが栽培されていた。しかし,現在では野菜作と家畜生産のための耕地内飼料作とが主体となっており,野菜畑では化学肥料,飼料畑では家畜ふん尿と化学肥料が多量に投入され,余剰窒素量が増えて,地下水の硝酸汚染が顕在化した。そして,でん粉輸入が1995年から関税割当制度に移行して事実上の輸入自由化となった影響を受けて,主力の一つのカンショも激減した。
こうした背景の下で,九州沖縄農業研究センターは,地下水質保全のための窒素負荷の削減とカンショ生産の復活を目指して,都城市の月野原台地で,カンショ-キャベツ輪作体系と飼料作物専作体系を軸に,1996~2000年にプロジェクト研究を実施した。その成果が2003年に刊行された(農林水産技術会議事務局編(2003)プロジェクト研究成果No.407.暖地畑作地帯における環境保全的畑作物生産技術の確立.全104ページ)。
●農業による窒素負荷の実態
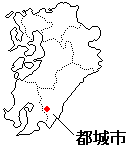
宮崎県都城市の月野原台地は総面積461ha,そのうち約320haが畑という畑作台地である。
都城市の施肥基準を基に台地の畑における年間の平均窒素収支を計算すると,1960年で120kgN/haだった余剰窒素(畑に投入された窒素量と搬出された窒素量の差)は,1994~1996年の平均で220kgN/haに増加した。実際には施肥基準を超える窒素が投入され,余剰窒素量はこれよりも多いと推察される。台地に流入する地下水の無機態窒素濃度は平均1.5mg/Lだが,台地からの湧水は平均9.6mg/Lと高く,民家の井戸水の平均値も8.7mg/Lの値を示しており,台地の畑に投入された余剰窒素が地下水の窒素を富化していることは明白であった。ただし,民家の井戸水は飲用に使われていない。また,1985年頃から家畜頭数の増加が頭打ちになり,1990~96年では地下水の窒素濃度の上昇も頭打ち傾向を示している。とはいえ,畑から最終的に河川に流出する窒素量は年間100~125kg/haに達していると推定された。
●窒素負荷削減技術の開発
成果のとりまとめの中で,山川理畑地利用部長(現所長)は,施肥基準が前後作を考慮していないと指摘している。すなわち,(1)実際にはカンショのツルが鋤き込まれているのに,ツルから供給される養分量を減肥する施肥基準になっていない。(2)また,家畜ふん尿を多量に施用して,土壌からの無機態窒素の供給量が多いはずなのに,それを考慮した施肥基準になっていないと記している。こうしたことから,実際には施肥基準を超える養分が投入されているはずであるプロジェクトではこれらを考慮すれば,かなりの減肥が可能なことが実験的に証明されている。
(1)夏作として取り入れられているギニアグラスを慣行のように5月に播種すると,作物体がまだ小さくて肥料吸収力の乏しいうちに梅雨となって,土壌中の窒素が溶脱される。そこで,前作のイタリアンライグラスの収穫時期を遅らせて,ギニアグラスを梅雨後の7月に播種する作期移動を行えば,溶脱量を減らせる。
(2)また,カンショや野菜の畦の表面を固くして,雨水を地下浸透しにくくすると,溶脱量を減らせる。
(3)さらに,カンショの生産効率を高めるために,苗を挿苗するのでなく,バレイショのように種イモを直接畑に植え付ける直播栽培を行って,野菜畑にカンショを導入すれば余剰窒素を減らせるし,裸地畑に導入すれば無駄に流亡する窒素を回収できる。
これらやその他に関する様々な実験を行った結果から,硝酸の溶脱を削減する技術を要約した。最も有効な対策技術は,搬出可能な作物残渣を圃場外に搬出・堆肥化することで,これによって余剰窒素の16~60%を削減できる。しかし,現行の農作業体系や経営形態ではこの作業は困難であり,残渣の鋤込みを前提とした対策として,下の表がまとめられた。
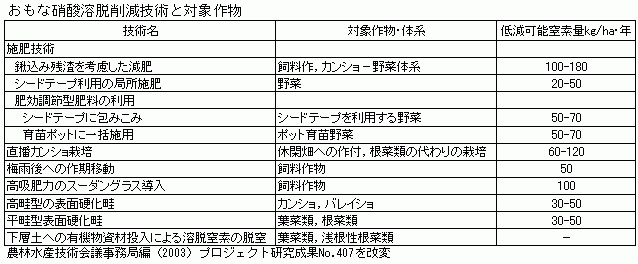
そして,カンショを野菜作や飼料作に積極的に取り込んだ環境保全的な作付体系も提案された。さらに,これらを支える技術として,直播栽培に適したカンショ品種の選定や栽培技術,表面を硬化しながら畦立てする作業機の改良,さらに,これらの技術を導入した輪作体系の経営評価も検討された。

畦表面硬化のためのアタッチメントと成型された畦の状態(撮影:生駒泰基)

土壌表面除草剤を同時散布できるようにしたもの(撮影:生駒泰基)
●誰が環境保全的農業のコストを負担するのか
本プロジェクト研究は,さらには農家の環境問題に対する意識も調査している。
栽培基準に従った施肥を前提として計算しても,1960年に比べて1996年には余剰窒素量が約2.3倍も増加しているが,農家の多くは,化学肥料は「栽培基準どおりに投入しているので過剰投入ではない」と回答している。このことから,化学肥料投入に対する農家の問題意識の改善と施肥基準の見直しが必要なことを指摘している。しかし,意識改善には大きな問題がある。それは,解決に要するコストをどうするかである。
窒素負荷削減技術の一つとして提案されている畦表面硬化について見てみよう(図2)。畦表面硬化機を導入すると減価償却費が増大し,手取り除草が必要となって労働時間が増加する。その一方で,カンショのA品率は上昇するが,収量低下が見込まれるため,ha当たりの全算入生産費は慣行栽培に比較して29万円増加し,農業所得は8.6万円低下すると推定される。この例のように,環境保全に要するコストを誰が負担するのかが問題になるのである。
農業者は現状の収益を確保できない技術は採択したくないと回答している。そこで,非農業者に誰が水質改善コストを負うべきかを質問した結果,9割の住民が農業者のみの責任に負わせるべきではないとの意識をもっているが,行政(財政)等が負担すべきか,地域住民(受益者)の直接負担まで容認するかについては意見が分かれていた。だが,少なくとも汚染者負担原則に従って農業者が負担すべきとの機械的適用は支持されていないと判断された。
「環境保全型農業レポート」の2004年9月1日号の「環境省が刊行! 主に農業に由来する地下水の硝酸汚染の実態と対策に関する事例集」に紹介したように,都城市の畑作台地における農業由来の地下水汚染は地元で問題になっている。そして,環境省の事例集でも,今後,納税者である市民に情報公開をしつつ,市税を投入して行う対策事業の事業評価も行って,市民の理解を得ることが大切であると指摘している。都城市では農業者にだけコスト負担を負わせるのでなく,市税の投入をあおいで問題解決に向かう条件が作られつつあると推定される。この方向で問題が解決されることが期待されるが,そのためには,窒素負荷削減の優良農業行為規範を定め,それを遵守することを条件に市税を投入することになろうが,規範の内容をどうするのか,いくら補償するのか,規範を遵守した農産物にラベル表示をして市民に少し高値でも購入してもらう制度を作るかなど,これから導入すべき新しい農業環境政策を農業者,市民,行政とともに研究サイドも一緒になって具体的に検討すべき段階にきていよう。
| ★養分の地下浸透とうね表面硬化に関連した記事を『ルーラル電子図書館』で検索するにはこちら → |
2.中央農業総合研究センターがIPMマニュアルを発行
●化学農薬半減のためのマニュアル
特別栽培農産物は,化学肥料の窒素成分量を慣行の5割以下にするとともに,化学合成農薬の使用回数を慣行的使用回数(土壌消毒剤,除草剤等の使用回数を含む)の5割以下にして生産しなければならない(環境保全型農業レポート,2004年7月1日号)。また,持続農業法に基づくエコファーマーでは,化学肥料窒素の施用量や化学農薬の散布回数を,慣行の2~3割削減することを規定している自治体が多い。では,病虫害を現在よりもひどくしないで,化学農薬の散布回数を5割以下にするには具体的にどうすれば良いのか。これに応える格好のマニュアルが発行された。
中央農業総合研究センターは1999~2003年度に,化学農薬使用量の大幅な削減を可能にする病害虫群管理技術の確立を目指したプロジェクト研究「環境負荷低減のための病害虫群高度管理技術の開発」(IPMプロジェクト)を実施し,その成果の一つとして,「IPMマニュアル~環境負荷低減のための病害虫総合管理技術マニュアル」を2004年9月に発行した(注:IPMは総合的病害虫管理と訳され,経済,健康および環境へのリスクが最小になるように,生物的,耕種的,物理的,化学的手段を組み合わせた持続的な病害虫管理体系)。
このマニュアルは,作物と地域を組み合わせた13の作目(施設トマト,施設ナス,施設メロン,キャベツ,カンキツ,ナシ,チャ,水稲(東日本),水稲(西日本),バレイショ,ダイズ(東日本)とダイズ(西日本)を対象にしている。現時点において現場で利用できる化学農薬によらない病害虫防除法と,その効果に影響を与えない化学農薬とを組合せて,病害虫の被害を経済的に許容できる範囲に抑える具体的防除体系を提言している。
各作目において,まず,化学農薬によらない技術で,現場で利用できる技術を,(1)病害虫抵抗性品種(穂木と台木),(2)生物的防除法および(3)物理的防除法に分けて解説している。例えば,施設トマトの場合,
(1)病害虫抵抗性品種(穂木と台木)では,品種名,その病害虫に対する抵抗性特性,適用作型,価格,メーカーを解説し,使用方法と使用上の留意点を記している。
(2)生物的防除法では,ハモグリバエに有効なイサエアヒメコバチとハモグリコマユバチ,コナジラミ類に有効なオンシツツヤコバチとサバクツヤコバチ,センチュウに有効なモナクロスポリウム・フィマトパガム剤とパスツーリア・ペネトランス剤,灰色かび病に有効なバチルス・ズブチリス剤について,商品名や価格も記して,対象病害虫と作用機構を解説し,使用方法および使用上の留意点を記している。
(3)物理的防除法では,防虫ネット,吸放湿性フィルム,近赤外線カットフィルム,土壌還元消毒(フスマまたは米ヌカ+灌水),根域制限栽培と太陽熱土壌消毒の併用,熱水土壌消毒について,対象病害虫と作用機構を解説し,使用方法および使用上の留意点を記している。
●作目ごとの具体的防除技術体系の提案
これらの現場で使える技術を組み合わせた具体的防除技術体系を,作目ごとにいくつかのケースについて一覧表で提示して解説している。例えば,施設トマトでは,南関東の半促成栽培で,センチュウが問題になる通常のケースを対象に,表1を提示している。この例では除草剤を除く化学農薬の使用回数が,慣行の20回を8回に削減できている。しかし,防除資材費が,想定したハウス面積(10a)で慣行の2.1倍の23.2万円に増加している。他の施設トマトの例でもIPM体系では防除資材費が2倍強となっている。次いで,将来利用可能な技術を解説している。例えば,施設トマトでは,トマト萎凋病に効果のあるカラシナの鋤き込み,センチュウとフザリウム属菌に効果のあるアミノ酸のメチオニン,トマトサビダニに効果のあるトマトツメナシコハリダニ,トマト萎凋病などに効果のある非病原性フザリウム菌株,トマトモザイクウイルスの弱毒株を解説し,これらも取り込んだ将来のIPM体系の事例も提示し,現在利用可能な技術を用いたIPM体系よりも,化学農薬の使用回数を減らすことができることを示している。
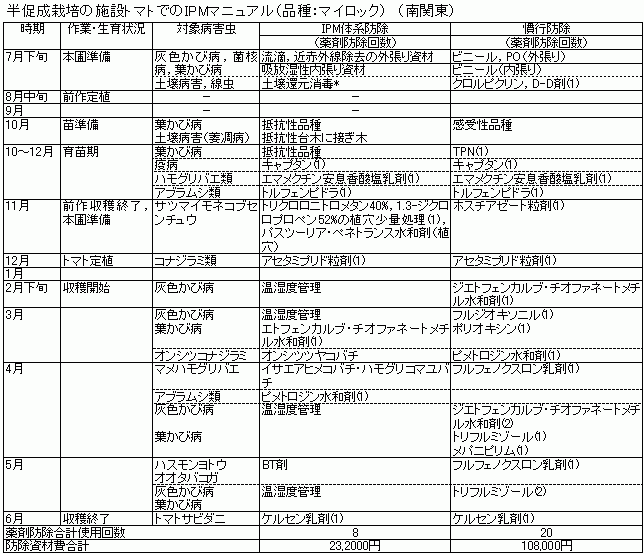
*1回のみ.2回目以降は植穴くん蒸処理
ハウス規模は,間口8m×3連棟×奥行き42m,軒高(肩まで)2.3m,棟高(峰の最高所まで)3.9m,勾配4寸(横に1m行って0.4m下がる),両側天窓の屋根型を想定。ビニール資材は機能性資材の価格と通常資材の差額を原価償却して計上。種子代も計上した。
▼総合防除については『総合防除の考え方と実際』で各作物での具体的な技術が紹介されている。
 西尾道徳(にしおみちのり) 西尾道徳(にしおみちのり) 東京都出身。昭和44年東北大学大学院農学研究科博士課程修了(土壌微生物学専攻)、同年農水省入省。草地試験場環境部長、農業研究センター企画調整部長、農業環境技術研究所長、筑波大学農林工学系教授を歴任。 著書に『土壌微生物の基礎知識』『土壌微生物とどうつきあうか』『有機栽培の基礎知識』など。ほかに『自然の中の人間シリーズ:微生物と人間』『土の絵本』『作物の生育と環境』『環境と農業』(いずれも農文協刊)など共著多数。 |