












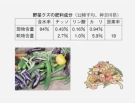

三平汁は塩漬けやぬか漬けの魚と野菜でつくる塩味の汁で、北海道の伝統的な魚の汁です。江戸後期に各地の民俗や歴史、地理などの記録を残した菅江《すがえ》真澄《ますみ》の日記『蝦夷喧辞辯《えみしのさえき》』にサンペ汁が掲載されており、「北海道」の命名者とされる松浦武四郎の『再航蝦夷《えぞ》日誌』にも記述……

かじかは別名「鍋こわし」、おいしくて鍋をつついて壊してしまうことから、こう呼ばれています。ややグロテスクな姿ですが、よいだしが出て魚の汁の中でも味がとくにおいしいです。新鮮なかじかが手に入るとまずつくるのが味噌汁で、残ったら塩でしめて三平汁にしました。北海道の最北に位置する稚内市は、宗谷海峡を挟……


さんまの水揚げ量が本州一の大船渡市で塩焼きと並ぶ定番料理が、すり身汁です。おかわりをして一人2杯は食べ、家族が少なくても多めにこの分量でつくり、温め直しながら食べます。 そのつくり方には産地ならではの特徴が見られ、まずさばく際には頭をちぎるようにして同時に皮をはぎとり、それから三枚におろします。……

真だらの頭、エラ、中骨、内臓などの「じゃっぱ」を使い、味噌味や塩味でつくる青森県の冬の郷土料理です。じゃっぱとは津軽弁で「雑把」の意味。以前は各家庭で年取り魚の真だらを一本まるまる購入すると身と白子、たらこをおかずや酒の肴にし、残ったじゃっぱを汁にしていました。頭から尾っぽまで捨てることがない始……

三陸沿岸で親しまれている冬の汁ものです。定置網で水揚げされたどんこは舌がふくらんで出ており、その見た目から「ベロ出しどんこ」と呼ばれます。 一般的に魚を汁に入れるときは刻んだ身やアラを使うことが多いですが、どんこは骨が細かく、身がやわらかく崩れやすいため、小さめのものは内臓をとったら丸ごと入れま……