

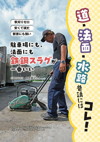








新鮮なさざえの身のコリコリっとした歯ごたえと、肝のほろ苦さを卵でとじた、旨みたっぷりのどんぶりです。海に囲まれた南房総でも、さざえやあわびはごちそうで、新鮮なとれたてを炭火焼きにするさざえのつぼ焼きやあわび焼きは、特別なハレの日や行事で奮発して食べるもの。やや小ぶりなさざえは、このようにどんぶり……

東播磨地方の中心部に位置する加古川市で、かつめしは誰もが認める地元の味です。皿に盛ったご飯の上に、切ったカツをのせデミグラスソース風のたれをかけ、カレー粉で風味をつけてボイルしたキャベツを添え、箸で食べます。カツは厚切りの牛カツが基本ですが、豚カツでもつくります。ここで紹介するレシピは牛の薄切り……

かつて炭鉱の町として大変栄えた夕張市は、内陸部ではありますが苫小牧《とまこまい》から運ばれた魚介類が魚屋に並び、行商も売りに来るので、日常的に新鮮な魚が入手できました。おいしい食べものは働く原動力になります。炭鉱で働く人たちは収入もよかったので、食材にかける金額は多く、ほっき貝は刺身や酢の物、バ……

昭和40年代、肉は高価であったことと脂身が子どもに好かれないこともあり、県西北部ではカレーといえばするめでした。するめは結婚式の引き出物としてもらうことが多く、どこの家庭にもだいたい常備されていました。 するめを裂くのは子どもの役割です。小さく裂いて水で戻しておくとうま味たっぷりのだしが出るので……

横浜市内でも農業がさかんな泉区で忙しいときに日常的につくられたのが、家で収穫した野菜と常備しているさばやいわしの缶詰を使ったカレーです。当時、肉は貴重品だったので滅多に口にすることはなく、さばカレーが一般的でした。 家にある食材ですぐにできるので夏にはよくつくり、近所からカレーのにおいが漂ってく……

日本海に面する府北部では、さば、あじ、いわし、かれいなどの魚介類が豊富に水揚げされ、中でもさばは早くから缶詰での利用が進みました。丹後地方の名物「ばらずし」も、さば缶でつくった味の濃いそぼろをたっぷり使うのが特徴です。さば缶はカレーライスの具にも好んで使われました。魚肉ソーセージのカレーとともに……

勝浦川流域の勝浦町や上勝町では、夏になると河原で新鮮な鮎となすやじゃがいも、玉ねぎなどで味噌仕立てのろうすい(雑炊)をつくります。この地域では「鮎の喰い川」と呼ぶ鮎の瀬張り漁が、漁業権をもつ人を中心に近所の人たちで行なわれます。川幅が広く流れの緩やかなところ(大川)で網を上流と下流から入れて鮎を……

県南西部の佐野市周辺は、夜は毎日のようにうどんを打って食べていた土地柄です。冷や汁(ひやじるとはいいません)はご飯にかけるのではなく、うどんのつけ汁として食べます。きゅうりの食感と香りのよい地粉のうどんののどごしもよく、夏には食べたくなる料理です。 ごまの香りと味噌の味がよく合います。ごまは自家……

おとうじの「とうじる」とは温めるという意味で「湯治《とうじ》」からきたといわれています。竹で編んだとうじかごにゆでた麺を入れ、具だくさんの汁の中で温め直して食べます。汁をつくり、麺をゆでておけば、すぐに出せるので、善光寺平では法事など人が集まるときによくつくられました。 「たくさん準備しています……

具だくさんの汁に「せんだご」を入れた天草の郷土料理です。せんだごとは、ゆでたさつまいもにさつまいもでんぷん(せん)を加えてこねたもの。畑作中心で水田が少ない天草では、昔からさつまいもは主食やおかず、おやつなどさまざまな料理に使われてきました。せんだご汁もそのひとつで、汁ものとしても食べられますが……

ちゃんぽんと皿うどんは中国出身の陳平順《チェンビンシュン》氏が明治に創業した「四海樓《しかいろう》」でつくられたのが元祖といわれ、長崎の歴史の中では新しいものです。冬は体が温まり、夏は暑気払いにと年中食べられています。ちゃんぽんは陳平順氏が従業員や留学生のためにつくり、出前の際スープがこぼれない……

スパゲッティナポリタンは、第二次世界大戦後に横浜の老舗ホテルの料理長によって考案されました。イタリアのナポリ発祥と思われるかもしれませんが、生まれは横浜です。ゆでたてのスパゲッティをケチャップではなくトマトソースで和えたもので、ホテルのメニューには現在もホテル発祥の料理として載っています。 一方……

埼玉県は日照時間が長く、気候もおだやかなことから、商業的にもまた自家用にも昔からさまざまな野菜が栽培されてきました。聞き書きをした入間《いるま》山間部、飯能《はんのう》市名栗《なぐり》は、平地が少なく米はつくれない土地でしたが、畑で小麦や大豆、いも、野菜を栽培し、山では山菜、木の実がとれました。……

そうめんを具とする味噌汁で、奈良盆地を中心とした県全域で食べられています。奈良盆地の中央に位置する桜井市三輪は三輪そうめんの生産地で、そうめん発祥の地ともいわれており、身近な素材です。 この味噌汁は日常食として一年を通して食べますが、とくに夏場は昼食の冷やしそうめんの残りを、その日の夕食や後日つ……

しか煮は、相模湾で秋にとれるヒラソウダと玉ねぎを甘辛く炒め煮にした真鶴《まなづる》町の家庭料理で、名前の由来は「鹿のような味がする」とも「魚の表皮がしかって(光って)いる」とも諸説あります。 古くは漁師料理で、漁船の調理当番が釣ったばかりのヒラソウダでつくった船員のまかない飯でした。船の性能がよ……

かつおのたたきは、高知の「おきゃく(宴会)」に欠かせないごちそうです。春のかつおはぷりぷりとした食感で香りがよく、脂がのった秋のかつおはとろっとした食感で重厚な味わい。それぞれの季節でたたきにして楽しんできました。市販のたたきはいぶした後に冷水にとり、火が通るのを止めていますが、家庭では冷水には……

えつは小骨が多いので骨切りが必要ですが、油との相性がよく骨ごと食べられるので、から揚げや南蛮漬けにするとおいしい魚です。骨ごとたたいてつくねにして揚げたり、骨も素揚げにして、骨せんべいにしたりします。最近は地元のイベントで、つくねを使ったえつバーガーも売り出されています。 日本では有明海にのみ生……

もともとは、いかのげそと野菜を刻んで一緒に揚げた料理です。青森県では、太平洋側に面した八戸魚港や日本海側の鰺ヶ沢《あじがさわ》漁港など各地でするめいかがたくさんとれ、最盛期の7月から10月には日常のおかずとしていかがよく食卓にのぼります。いかの胴の部分は細く切って刺身にすることが多いですが、いか……

玉ねぎの甘味とえびの歯ごたえが絶妙なかき揚げは、富山湾に臨む富山市岩瀬では家庭料理の定番としておかずや丼の具としてよくつくられてきました。えびが重なったところはカリッと揚がらないので、なるべく薄く揚げるのがコツです。また、タネの段階で少しだけ塩を加えてえびの甘味を引き立てています。 白えびは水深……

石狩鍋とは鮭を使った味噌味の鍋のことです。かつて石狩川河口は、秋になると産卵のために川に戻る鮭が押し寄せ、明治時代には地曳《び》き網漁で100万匹以上の鮭が捕獲されていました。漁夫のまかない食でもあった塩味のアラ汁(三平汁)がやがて醤油味や味噌味の台鍋《だいなべ》として親しまれるようになり、昭和……