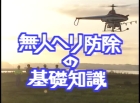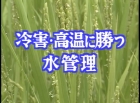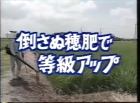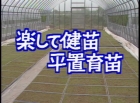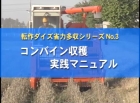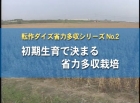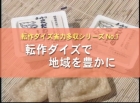豊後水道《ぶんごすいどう》、米水津《よのうづ》港でとれた小あじ(ぜんご)と赤じそを使った色鮮やかな姿ずしです。 米水津は起伏に富んだリアス式海岸の沿岸漁業がさかんな地域。家と海の距離も近く、家の前の岸壁からあじを釣ることができるほどです。昔は、祭りや運動会などの行事、来客がある度に、親戚の漁師や……

西濃地域の海津《かいづ》市は木曽三川(木曽川、長良《ながら》川、揖斐《いび》川)沿いで集落全体を堤防で囲んだ「輪中《わじゅう》地帯」として有名で、特有の川魚の食文化が残っています。川魚が多くとれた昔は、鯉やふなを鯉こく、ふな味噌、姿煮などにしてふるまいました。 ふな味噌はふなと大豆と味噌のうま味……

らっきょうよりも「らっきょ」と呼ぶのが福井流です。福井県は戦前には日本一の生産量を誇りました。現在でも全国で6位(2016年)の収穫量があります。とくに三国の三陸浜の砂丘地帯で多く生産される“花らっきょ”は有名で、小粒で純白、肉質がきめ細かで品質が良いといわれています。栽培方法が独特で、通常は8……

県南部の三戸《さんのへ》町は昔から食用菊の産地で、なかでも鮮やかな黄色い菊「安房宮《あぼうきゅう》」の生産がさかんです。安房宮は、江戸時代に京都の公家、九条家から観賞用にもらいうけた南部藩主が、香り豊かで甘味がありおいしかったため食用として広めたといわれています。三戸では酢の物や和え物、おひたし……

福島の家庭では、初夏になると蒸した米と米麹の漬け床で、きゅうりやなす、にんじんなどの野菜を漬けた三五八漬けが頻繁に食卓に並びます。名前の由来は、漬け床に使う塩と麹、米の容量が3:5:8になっていることから。野菜を漬けると、翌朝にはできあがります。とれたての夏野菜に塩けとご飯、麹の甘味がしみこみ、……

米ぬかに塩、水を混ぜて発酵させたものを漬け床として、野菜を短期間漬けたものがぬか漬けで、独特の香りが特徴です。 聞き書きの調査地である加須市、埼玉県東部低地は利根川の中流域に位置し、年間を通じて野菜が多くとれるため、保存食の必要がない地域でした。昔から物資の流通もさかんだったので、冬季に保存を目……

料理名の由来はやたらに何でも漬けこむことから、とも、やたらにおいしいから、ともいわれます。このやたら漬けがつくられてきたのは、三方を1000m級の山々に囲まれた県西部の千種《ちくさ》町(現宍粟《しそう》市)の中でも一番奥まった山間部の西河内《にしごうち》で、すぐ近くはスキー場です。雪深い冬を過ご……

福岡の夏の料理で、とくに人が集まるお盆の時期につくられ、仏様にお供えしたりお盆参り客にふるまわれます。甘味と酸味、野菜の旨みと味のバランスがよいピクルス風の料理で、名前はポルトガル語で漬物を意味する「アチャール」に由来するとも、「あちら(外国)」がなまったともいわれます。 材料は歯ごたえのある夏……

きのこの辛子漬けのことを「なばのからせ漬け」と呼びます。使うきのこは何でもよいですが、大分では、家の近くの山で栽培している椎茸でつくることが多いです。干し椎茸を使うと一年中つくれるうえ、歯ごたえもよくなります。噛むと甘辛く煮た椎茸のうま味が広がり、辛子の辛みがあとをひきます。ご飯の供にもお茶うけ……

地漬は、亜熱帯性の気候の中で、塩と黒糖で野菜を長期に保存できる沖縄の代表的な漬物です。主に茶うけとして、またおかずの一品として食べられてきました。地漬の歴史は古く、琉球王朝時代に中国からの使節をもてなした際の献立に「地漬大根」の記載があります。 地漬は、黒糖の甘みもある独特な味です。べっ甲色にな……

大根、にんじん、キャベツなどの野菜と身欠きにしんに麹を加えて低温下で発酵させた、北海道定番の漬物です。にしんのうま味と麹の甘味、ほどよい酸味はクセになる味で、正月にはざく切り野菜と黒いにしんを入れたどんぶりが、他の料理とともに食卓に並びます。 北海道は初冬から春まで雪におおわれます。昔は長い冬を……

昆布とするめを細切りにして醤油たれに漬けこんだ松前漬けは、松前の各家庭で一年中つくられます。昆布は、松前地方特産の「ホソメ」と呼ばれるものです。町の施設には松前漬け用の裁断機があり、正月が近づくと家庭ごとにホソメと新物のするめを持って切りに行きます。正月以降に食べる分もふくめ1年分を切るので、1……

千島海流と日本海流、対馬海流の三つの海流が流れこむ三陸沿岸は、水温や水流など、わかめの生育に適した環境がそろっており、昔から養殖がさかんな地域です。山々の雪解け水が注ぐ海は栄養分も豊富で、歯ごたえのよい、香り豊かなわかめが育ちます。 出荷されるのは主にわかめの葉の部分です。地域の人たちは残った根……

県北地域や中通り、会津など県内各地で広く食べられている家庭料理で、松前漬け(『漬物・佃煮・なめ味噌』p77)のルーツともいわれています。基本はせん切りにしたにんじんと細切りのするめを醤油味の調味液に漬けるシンプルなものですが、しょうがや昆布、ひじき、白ごまなどを加えたり、砂糖を入れなかったりと各……

にしんと大根を麹で漬けこんだ、旨みの深い保存食で、江戸時代からつくれらてきたと伝えられています。にしんは、昔は大量に水揚げされた貴重なたんぱく源であり、麹と漬けることで野菜に旨みやコクを与えました。かつては夏もきゅうり、なす、うりなどと一緒に漬けたにしんずしをつくりましたが、最近では気温が高く発……

「きっこうし」とは中越地区の方言で切ってぼっこす(壊す)という意味の「きっこす=乱切りにする、なた切り」から来ています。大根はよく味がしみるように、わざと不ぞろいに、なたの刃を斜めに半分ほど入れてから手首を返して切りました。「ねせ麹」は水分の少ない甘酒のもとのような感じで濃厚で、じっくり漬けるこ……

県内各地には湖魚《こぎょ》を煮つけて食べる習慣が根づいています。湖魚にはイサザ、モロコ、ゴリなどさまざまな魚がいますが、よく食べられているのが小鮎です。小鮎とは琵琶湖内で育った鮎のこと。普通、川で育った鮎は20㎝ほどになりますが、小鮎は成長しても10㎝ほどの大きさで、煮ると骨までやわらかく、丸ご……

徳島では煮豆というと金時豆が親しまれており、かき混ぜ(五目ずし)やお好み焼きにも入れます。おせち料理の煮豆も黒豆よりは金時豆が多く、正月には甘煮だけを食べるよりも、甘煮と根菜類と一緒に炊いた「れんぶ」が県下全域で食べられてきました。建前《たてまえ》(新築祝い)にも大鍋いっぱいにつくって昼食にふる……

東部低地の加須《かぞ》市の夏の日常食です。梅酢で漬け、夏の新鮮な大根のおいしさを引き出したさっぱりした漬物で、昭和30年代から今でもつくられています。加須市は利根川の中流域に位置し、温暖な地域なので、冬でも野菜に困りません。漬物は保存食というより、旬の野菜の味を楽しむものが多いです。