| 電子図書館 > 農業技術大系 > 追録 |  |
農業技術大系・土肥編 2012年版(追録第23号)
東日本大震災――津波,原子力事故による農地汚染に挑む
2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震による農地の被害は津波による浸水(写真1),福島第一原子力発電所事故の放射性物質による汚染が広域にわたっている。いずれも汚染対策は長期戦が予想され,研究機関ではさまざまな方法が試行中であるが,ちまたでは実効性がほとんど期待できない非科学的な憶測も大量に飛び交っている。今回の追録では,今現在わかっている科学的知見を中心に,専門家による確度・精度の高い情報を届けたい(第3巻)。

写真1 海岸に近く,がれきの多い激甚被災水田。「東日本大震災における津波被災農地の塩害対策」から
?放射性物質による汚染とその対策
最初の記事「農産物から人への放射性物質の移行を理解するための基礎知識」は,専門的な用語の解説,チェルノブイリ原子力発電所事故との比較,大気圏核実験で放出された放射性物質の特徴,放射性物質の農作物への移行,摂取による人体への移行,農耕地からの被曝について,全般的な理解を助けるため,環境科学技術研究所・塚田祥文氏,国際農林水産業研究センター・鳥山和伸氏が解説している。
たとえば,肥料分でもあり,人体にとって必須元素であるカリウムのなかには放射性カリウム(K-40)が存在する。土壌中には平均的な濃度の計算で300Bq/kg分あり,農作物中には白米で20Bq/kg,根菜類,葉茎菜類,果菜類などで数百から数千Bq/kg(いずれも乾物)相当が含まれ,毎日摂取している。
いっぽう,土壌中の放射性セシウム濃度が上限値5,000Bq/kgを下まわれば,移行係数による算出で代表的な農作物中の放射性セシウム濃度も6~29Bq/kgを下まわると推定できる。これは農作物の放射性セシウム暫定規制値500Bq/kgはもちろん,農作物中の放射性カリウム濃度19~157Bq/kg(いずれも現物)をも下まわる。
放射性セシウムのような人工放射性物質と,放射性カリウムのような天然放射性物質とで被曝に違いはない。無用な(追加的)被曝を低減化することは重要であるが,過剰な対応も避けるべきである。過度な対策は,農地の生産力を損なうだけでなく,無用な風評被害を生み出しかねない。生産者,消費者ともに,放射線を正しく理解し,科学的根拠に基づく,汚染レベルに応じた効率的対策が求められる。
さらに京都府立大学・中尾淳氏,農業環境技術研究所・山口紀子氏が「放射性物質の土壌中での動き」について解説(図1)。また,環境科学技術研究所・塚田祥文氏,武田晃氏が「放射性核種の作物への移行」について解説している。
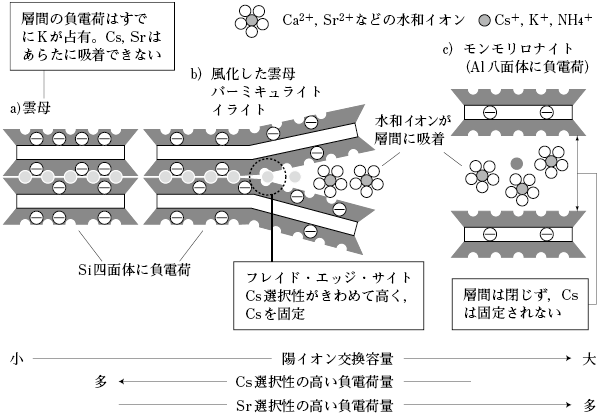
図1 2:1型層状ケイ酸塩鉱物の構造由来の負電荷とCs(セシウム),Sr(ストロンチウム)の吸着の関係
?農地の津波被害とその対策
津波や高潮による海水の突発的な浸水は,塩化ナトリウムを主成分とした多量の塩分を土壌にもたらし,作物に塩害を引き起こす。おもな塩分はカルシウム,マグネシウム,ナトリウムの塩化物,硫酸塩および炭酸塩である。さらに,河底・海底のヘドロ状堆積物や土砂,それにともなう多様な物質ももたらしたり,農業の持続性を破壊する,作土の消失をもたらす場合もある。
津波や高潮が農地にもたらすもの,+++塩害の原因と予測指標,除塩方法と除塩後の土壌管理について,東北大学・伊藤豊彰氏と菅野均志氏が「津波,高潮による農地被害の原因と修復の考え方」で解説。
また,現在進行中の取組みとして,「東日本大震災における津波被災農地の塩害対策」では東京農業大学・後藤逸男氏と稲垣開生氏が福島県相馬市における塩害被災農地の分類,農地の表面に堆積した津波土砂の土壌化学性,重金属含有量,復興支援方針,イチゴハウスや水田の除塩状況,除塩対策への提言について紹介している。
「灌漑水による除塩」では,農村工学研究所・原口暢朗氏が塩害,過去の津波や高潮災害と灌漑水による除塩対策,灌漑水による除塩方法,作物の耐塩性と除塩の目標値,灌漑水を用いた除塩の実例,その他の留意点について紹介。
「雨水の浸透除塩と弾丸暗渠」では,宮城大学・千葉克己氏が塩害と排水施設の損壊,調査地域の津波被害,暗渠の構造と排水のしくみ,調査圃場と調査方法,本暗渠のみの除塩効果,弾丸暗渠の施工による除塩効果の向上,弾丸暗渠施行後の圃場の耕起について紹介している(以上,第3巻)。
そのほかの企画――有機物活用,施肥改善,水分管理,情報技術など
?混植や緑肥,身近な有機物の活用
キャベツやブロッコリーなどでは,チョウ目害虫やアブラムシによる被害を受けやすく,有機栽培がむずかしい。そこで,山梨県内の有機栽培農家の実践を踏まえ,山梨県総合農業技術センター・赤池一彦氏が混作や間作,雑草草生の効果を実証。圃場に自生する自然雑草を虫害軽減に活かし,雑草やシロクローバの草生利用に加え,ネギ類の同時作付けやレタスの隣接作付けなど,混作が虫害軽減効果をさらに高める。
また近年,水田土壌の窒素肥沃度が低下し,高温年のイネの玄米品質の低下やダイズの収量低下の要因になっている。そこで,冬作のオオムギ栽培後に夏作緑肥(ヒマワリ,ソルガム,クロタラリア)を作付けする体系,イネ栽培後に冬作緑肥(ヘアリーベッチ)を作付けする体系を開発。富山県農林水産総合技術センター農業研究所・齊藤毅氏が紹介する。
身近な有機物の活用では,ホウレンソウ栽培でのコナダニ対策がある。コナダニは土壌消毒による防除効果が高いものの,ハウス周辺部からの侵入により,長期にわたる防除効果が期待できない。そこで,広島県立総合技術研究所農業技術センター・星野滋氏が土着天敵を活かした総合的な防除技術を開発した。土壌消毒直後のハウス内周辺部に稲わらを設置し,捕食性ダニ類などの天敵を増加させ,被害を抑制する(以上,第5-(1)巻)。
また,ハウスの外に山積みに放置されたトマトの茎葉は,見苦しいうえに,そこから再生したトマトに黄化葉巻病などの病気が蔓延し,感染源となる可能性がある。そこで,畜産でのサイレージ(乳酸発酵)技術を応用し,トマトの茎葉をポリエチレン袋に充填し,密封すれば,根腐萎凋病菌の繁殖を抑制でき,圃場への還元施用が可能である。千葉県農林総合研究センター北総園芸研究所・草川知行氏が紹介(第7-(1)巻)。
?施肥改善による生育改善,経営改善
北海道では被覆の除去が冬のわずかな期間に限られるハウスが多く,余剰栄養塩類が下層の根域内に残存している。そこで,従来の作土層よりも下層に残存する窒素を診断。根系が深くに到達する作物では,下層土に存在する硝酸態窒素を評価して施肥量を決定する。また,堆肥を施用するさいは土壌中に供給される窒素,リン酸,カリウムの各相当量を施肥量から減らす。北海道花・野菜技術センター・林哲央氏が解説(第4巻)。
また,土壌に過剰な養分があれば,その成分を少なくした肥料で施肥コストが削減でき,適正な土壌養分で作物の生育や品質・収量も向上する。たとえば,水稲ならリン酸とカリの収奪量,つまり籾がらと玄米による持出し量を考慮する。このような低成分肥料について,JA全農営農・技術センター・日高秀俊氏が紹介(第7-(1)巻)。
お茶の生産現場では収量,品質の向上をめざすあまり,基準を超えた施肥が行なわれている圃場も少なくない。そこで,窒素50kg/10a程度の施肥低減下で高品質茶を生産するための管理技術を福岡県農業総合試験場・堺田輝貴氏が追究。春肥や芽出し肥の割合を高くした春季重点型の施肥体系である(第6-(2)巻)。
いっぽう,施肥改善では畑や野菜を見ることも大切である。高知県四万十町で年間約60種類の野菜をつくっている桐島正一氏は,ナスで雌ずいや枝の長さ,オクラで葉の刻み具合,ニラで細い葉など,形の変化を追肥の目安にしている。そのほか,葉の色を見て追肥するショウガ,ラッカセイ,ニンジン,ナバナ,近くの雑草を見て追肥するサトイモ,エンドウ,基肥主体のちりめんカラシナ,ゴボウ,ダイコンなど,「生育診断による施肥で露地野菜の多品目少量栽培」で紹介(第6-(1)巻)。
そのほか,根株の充実によって増収を図る「アスパラガス伏込み促成栽培における亜リン酸肥料の葉面散布」について福島県農業総合センター・芳賀紀之氏が紹介している(第7-(1)巻)。
?適切な水分管理による生産性の向上
ホウレンソウの硝酸塩とシュウ酸塩濃度を同時に低減するには,どのような技術の組合わせが必要か? 神奈川県農業技術センター・北宜裕氏,上西愛子氏によると,施肥量を半減し,収穫前に十分な灌水を行なえば,経済レベルでの品質低下を引き起こさずに硝酸塩濃度を低減できる。シュウ酸塩濃度は,施肥量や収穫直前の灌水の影響が少なく,品種特性すなわち生育スピードの差の影響がきわめて強いことから,適切な品種を選ぶことで低減できる(第2巻)。
また,北海道で転換畑が多い道央圏では,コムギの収量や品質にバラツキが大きい。粘質,堅密で土壌構造が未発達な圃場が多く,生育初期には透排水性の不良による湿害が生じ,生育後期には根張り不足や水分不足が生育を規制する場面が見られる。そこで,圃場内に幅,深さともに30cm程度の明渠を形成することで,越冬前から春先にかけての排水促進と,水田用水路から明渠への通水による水分供給を可能にした。北海道中央農業試験場・塚本康貴氏が紹介(第5-(1)巻)。
同様に近年は雨が短期間で多量に降ることがあり,ニンジン圃場では冠水が数日間に及ぶ例も見られるようになった。湿害回避には圃場の排水性を改善する必要があるものの,圃場整備による排水対策がとれない場合は耕種的手段が必要となる。そこで,湿害に強い品種の選定,湿害を生じる地下水位と湛水期間,高うねによる湿害回避,それらを組み合わせて降雨被害を軽減する技術を草川知行氏(前出)が紹介(第3巻)。
?新しいシステム,情報技術の活用
高設栽培は培地が少量で,地面から隔離されている。この構造が,じつは温暖化の影響を受けやすくする原因となっている。イチゴの生長点はクラウンと呼ばれる地ぎわ付近の内部に位置しているため,高設栽培では培地温度が高くなると,秋口に栄養生長から生殖生長へと移行しにくい環境が形成される。また,イチゴは,体内窒素濃度が低い状態では花芽が誘導されやすいいっぽう,やがて生育が低下し収量も減少する。体内窒素濃度が高い状態では,生育や収量性は優れるが花芽を誘導しにくい状況となる。そこで培地冷却法と肥効調節型肥料を組み合わせた中休み軽減技術を追究。近畿中国四国農業研究センター・山崎敬亮氏が紹介。
そのほか,養液の平均水滴径を10μm以下の超微粒子にして,浮遊しやすくて蒸発しやすい超微霧(もや)状の液肥で活用する「野菜のドライフォグ噴霧養液栽培システム」を神戸大学・金地通生氏が紹介(以上,第6-(1)巻)。
トラクタ装着型の光ファイバーを利用して可視・近赤外光の土壌面照射とその反射光スペクトルの観測を連続して行なう「リアルタイム土壌センサを用いた土壌施肥管理――農業法人あぐりの試み」を東京農工大学・澁澤栄氏が紹介。
土壌診断データの一元的蓄積を行ないながら,施肥設計は利用者が個別にソフトウェアをカスタマイズできる「神奈川県土壌診断・施肥設計プログラム」を神奈川県農業技術センター・佐藤忠恭氏,岡本保氏が紹介(以上,第4巻)。
?脱・臭化メチルへの土壌病害対策
臭化メチルは「モントリオール議定書」でオゾン層破壊物質に指定され,先進諸国では2005年に全廃することが決定された。日本では,ショウガで有効な代替技術が未確立という理由から不可欠用途として使用が認められてきたが,2013年に全廃することを宣言した。そのような背景のもと,高知県農業振興部・竹内繁治氏が土壌くん蒸剤と殺菌剤を組み合わせた防除法を開発。臭化メチルに代わる低コストで効果の高い方法である。
また,栽培期間が1~2か月程度のホウレンソウ栽培で熱水土壌消毒を行なう場合,施設トマトやバラ栽培と同等の熱水処理量(200~300l/m2)では多すぎ,コストも見合わない。そこで,前出の北宜裕氏は,防除効果が高く,生育と収量を最適化できる処理量を検討。100l/m2最少・最適であることを明らかにした。
そのほか,簡易な設備で短時間で正確に行なえる「RT-LAMP法を活用したキュウリ緑斑モザイク病の診断」について愛知県農業総合試験場・福田至朗氏が紹介している(以上,第5-(1)巻)。